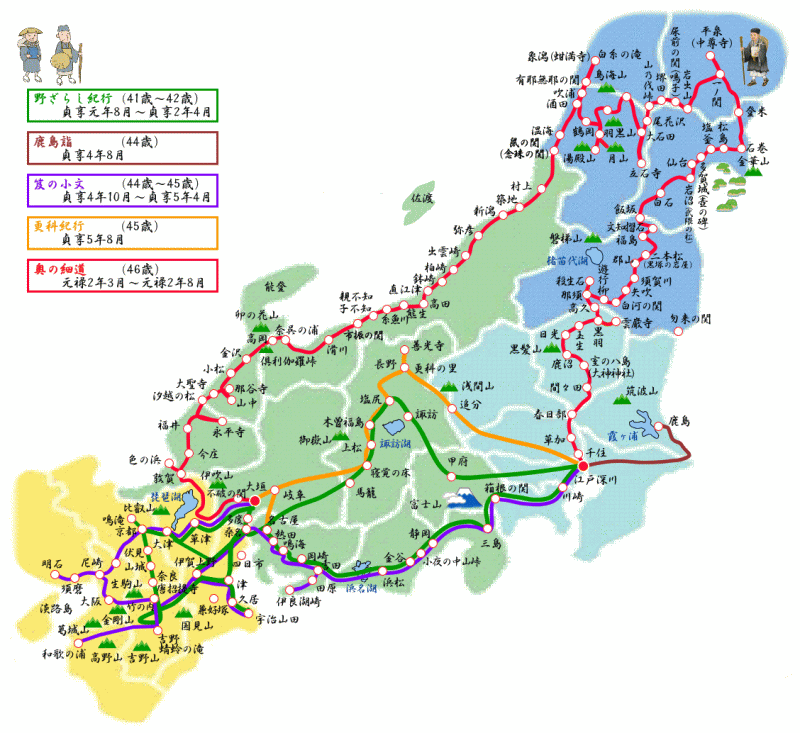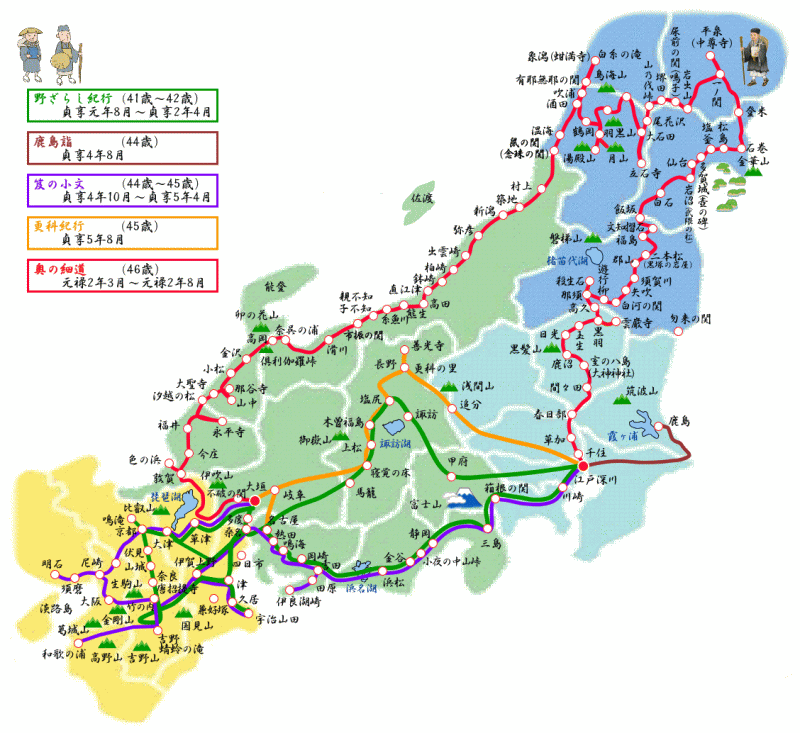|
美しい日本の風景を「五・七・五」の十七音で表現する俳句は、四季をもつ日本ならではの文化です。
俳句はもともと室町時代に流行した連歌から発展した「俳諧」(はいかい)がもとになっており、
言葉遊びの要素が大きなものでした。それに芸術性を持たせた人が、
江戸時代の俳人・松尾芭蕉(まつおばしょう)です。
松尾芭蕉は日本を代表する俳人で、最初は松尾宗房(まつおむねふさ)と名乗っていました。
農民の生まれだとされていますが、幼少期のことはよくわかっていません。
やがて北村季吟(きたむらきぎん)に師事して俳句の世界に足を踏み入れます。
松尾芭蕉と言えば『奥の細道』が有名です。これは松尾芭蕉が現在の東北や北陸で旅をしながら
作った紀行文で、文中に多くの俳句があり、「夏草や兵(つわもの)どもが夢の跡」
「閑(しずか)さや岩にしみ入る蝉の声」などの有名な俳句もこの中に収められています。
松尾芭蕉は『奥の細道』を作る前にも、紀行文『野ざらし紀行』を発表していますが、
やはり多くの俳句が入っています。このように旅をしながら全国を回っていたことや、
伊賀忍者で有名な現在の三重県伊賀市出身という説があることから
「松尾芭蕉は隠密(忍者)なのでは?」ともささやかれています。
『奥の細道』で松尾芭蕉が歩いたとされる距離は、約2400キロメートルにもなります。
山道も多いこの道を、松尾芭蕉は約150日間かけて歩いています。
これを1日の移動距離にすると約16キロメートルになりますが、
実際には移動をしない日もあり、1日で50キロメートルも移動しているときもあります。
これを45歳の初老(当時)の男性が歩いたとすると、非常に元気です。
また当時は関所(税の取り立てや検問をするための施設のこと)等での取り締まりも
厳しいですし、何日も泊まりがけで旅をするため、とてもお金がかかります。
一般庶民が気軽に旅などできる時代ではありませんでした。
そんな時代において、松尾芭蕉は何回も長旅に出ています。
また『奥の細道』の旅に同行した弟子の河合曾良(かわいそら)によると、
絶賛した『松島』にはさほど滞在せず、仙台藩の重要拠点である「石巻港」や
『瑞巌寺』(ずいがんじ)などを興味深そうに見て回ったそうです。
真相は明らかになっていませんが、忍者説というのも大変興味深いものです。 |
|
|