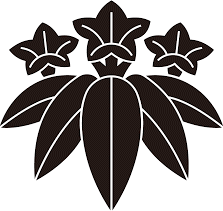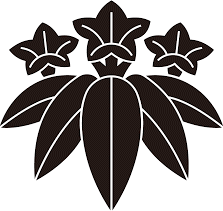|
|
 笹竜胆(ささりんどう)は源氏の家紋~? 笹竜胆(ささりんどう)は源氏の家紋~? |
| |
|
「リンドウ」は晩秋に藍紫の鐘状の花を咲かせる野草で、
葉が笹に似ているので「ササリンドウ」とも呼ばれます。
「竜胆」とは漢名で、根の味が竜の胆のように苦いことから
名付けられたといいます。古来より愛された草花「リンドウ」は
『万葉集』や『枕草子』にも登場します。
平安時代には紋様として、衣装・調度品・乗り物などの装飾に
使われました。鎌倉時代初期には家紋化したと考えられており、
公家の間で多く用いられました。
源氏を代表する家紋と思われている「笹竜胆」を家紋として多く
使用していたのは、実は清和源氏とは系統が異なる村上源氏でした。
その事実が後々の世で混同され、清和源氏の後裔を称する家なども
笹竜胆を家紋として使用するようになり、
いつしか源氏全体の代表紋であるかのように
認識されるようになったのです。
村上源氏がよく使用していた家紋「笹竜胆」は、
竜胆の花と葉をかたどった紋で、花三、葉五を基本としています。 |
|
 家紋追記~ 家紋追記~ |
|
竜胆の花に,葉をあしらった模様または家紋。
その葉が笹に似ているところからこの名称がおこったものですが、
元来、竜胆と笹の合成模様ではなく、通常、葉を笹のように五葉並べ、
その上に花を三つ添えた形式をとっています。
これは清和(せいわ)源氏の家紋と伝えられますが、確証はありません。
1390年(元中7・明徳1)に奉納された、熊野速玉(はやたま)大社の
直衣(のうし)(国宝古神宝のうち)にみられる竜胆唐草は、
笹竜胆に近い形式です。
鎌倉幕府を開いた源頼朝は、清和源氏の流れの河内源氏の嫡流に
生まれました。頼朝は、平治の乱で敗れたあと伊豆に配流され、
20年に及ぶ流人生活を送ります。しかしその後、打倒平氏が成ると、
鎌倉幕府を開き武家政権を確立させました。
このように群をぬく政治力をみせた頼朝でしたが、厳格さの故に
義経ら一族を粛清してしまいます。それが遠因となって、
頼朝の死後20年にして源氏の嫡流は滅ぶことになったのです。 |
|