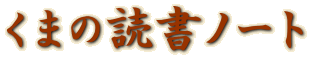
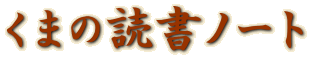
くまは、読書を好む。ただし、その読み方には節操がなく、ポリシーも感じられない。ひたすら「つれづれなるままに」
読むのである。寝床、トイレがおもな読書場所であるが、これは、わが家のちびっこギャングに襲われない、限られた
オアシスであるが故である。そのくまが最近読んだ書と、感想を以下に記す。
| 「SEVEN YEARS IN JAPAN」 D.ストイコビッチ 祥伝社黄金文庫 01年10月 |
ピクシーが半生を振り返った書。相当、自分自身に自信を持った内容では あるが、決して嫌味っぽくはない。サッカーにはあまり詳しくないが、彼が 偉大な選手であったことは素人目でも分かる。これからの日本サッカーの 在り方など、将来に向けてのアドバイスなども簡潔に書かれており、読み 易さとともに、ますます彼の人柄を感じた。 |
| 「俄−浪華遊侠伝−」 司馬遼太郎 講談社文庫 |
|
| 「『勝ち組』の構想力」 大前研一 田原総一朗 PHP研究所 01年9月〜10月 |
|
| 「巨人がプロ野球を ダメにした」 海老沢泰久 講談社+α文庫 01年8月〜9月 |
ついついタイトルで購入してしまった。決してアンチ・ジャイアンツではない と思っているのだが…。この書では、巨人だけではなく、日本のプロ野球 がなぜおもしろくなくなったのかを考察している。最近のMLB流行もある のだが、本当に「プロ野球」の行く末が案じられる。 |
| 「サザエさんの秘密」 世田谷サザエさん研究会 データハウス 01年9月 |
この手のものが、数年前に流行りましたよね。「サザエさん」は、日本が世 界に誇る三大アニメ(私が勝手に決めた)の1つであり、日本人の心でも ある。ちなみに、残りの2つは、「ドラえもん」と「アンパンマン」。 |
| 「日本はなぜ 負ける戦争をしたのか。」 田原総一朗 アスキー 01年8月 |
「朝までテレビ」で放映されたものを再編集したもの。戦争問題はやはり 複雑だ。その責任の所在も、いまや明確にはできないだろう。昨今、アジ アの近隣国から再び「戦争に対する考え方」に対して集中砲火を浴びて いるが、そんな議論を繰り返すことにどんな価値があるのだろうか。 |
| 「プロ野球 問題だらけの12球団」 小関順二 草心社 01年6月〜7月 |
プロ野球12球団の戦力分析(フロントの強さも含めた)を中心に、各球団 の3年後を、筆者がおしはかっている。この書は、2年前に書かれたもの なので、現状との比較ができておもしろい。筆者の分析はなかなか鋭い。 特にドラフトに対する球団の姿勢などは興味深いものだ。 |
| 「へたな頭の使い方で 一生を終わるな!」 鈴木健二 三笠書房 01年6月〜7月 |
書かれていることはいちいち正論なのだが、鈴木健二のキャラを、私は 素直に受け入れられなかった。したがって、書評もなし。 |
| 「『NO』と言える日本」 石原慎太郎 盛田昭夫 光文社 01年6月〜7月 |
大ベストセラーとなったこの書を、古書で購入した。10年ほど前の執筆な ので、かえってその時に予言している内容との比較ができておもしろい。 デタラメなこと(おもに石原の発言)も当然あるが、2人の先見性はやはり 特筆ものだ。 |
| 「ハリウッドの日本人」 垣井道弘 文藝春秋 01年6月 |
「日本人は果たしてハリウッド・スターになれるのか」という疑問が私の中 にはある。映画環境だけではなく、俳優としての資質が根本的に違うの では。石橋貴明あたりが、日本の代表的なアクターと思われては何とも 恥ずかしい限りだ。「ブラック・レイン」なんかもちゃっちいしなあ…。 |
| 「政治的に 正しいおとぎ話」 ジェームズ・ガーナー DHC 01年6月 |
少し前にはやった、童話のいじりもの。読み始めは、おもしろかったのだ が、読み進むうちに、少しくどくなってきた。一応、最後まで読みきったが、 後半は相当飽きてしまった。ふと、気が付いたのは、翻訳にデーブ・スペ クターが携わっていたこと。くどいわけだ。 |
| 「やった。」 坂本 達 ミキハウス 01年6月 |
4年半の有給休暇をとって、世界一周を自転車で成し遂げた男の体験 談&写真の数々。生死を賭けたこの試みには、正直、「すげ〜」という 言葉しか出てこない。私自身も、高校時代に自転車で京都・奈良まで 行った経験はあるが、ここまではとてもじゃないが…。この人、確かに 凄いのだけど、結局、強力なスポンサーがいて、こんな思い切ったこと ができるわけで、これを自費で実践していたらもっと尊敬できるのだけど。 でも、日本一周くらいは、いつか成し遂げたいなあ。 |
| 「新撰組血風録」 司馬遼太郎 角川文庫 01年5月〜6月 |
やはり、幕末を書かせれば、司馬の右に出るものはいない。以前、「燃え よ剣」で、新撰組は読んでいたので、一体何が違うんだろうというのがし ばらくの疑問であった。「燃えよ剣」が、近藤勇、土方歳三、沖田総司ら いわゆる新撰組の幹部を中心に描いたのに対して、この作品では、平 隊士をも含めた様々なストーリーから成っている。人斬り集団の人情味 あふれる挿話の数々である。 |
| 「ジャパンモデル」 田原総一朗 PHP 01年5月完読 |
内容的には、前出「勝つ日本」にオーバーラップする。サブタイトルとなっ ている「日本が米国を再び追い抜く日」が気に入った。こんな時代であれ こそ、日本人としての自覚と誇りが必要なのだと思う。やっぱり、前向き に物事を考えていかなければ。 |
| 「勝つ日本」 石原慎太郎 田原総一朗 文藝春秋 01年5月完読 |
前出「日本のカラクリ」の内容も相当辛らつであったが、これに石原慎太 郎が加わることにより、いよいよ歯止めが効かなくなった。石原の書は これ以前に読んだことがなかったので、「何となくやんちゃな人」というイ メージのみ私の中にはあった。「北朝鮮のテポドンが京都あたりに落ち れば良かった。」と大まじめに語っている。怖い。この書のおもしろさは、 石原と田原は互いに持論を曲げることが無く、したがって、歩み寄ろうと する姿勢がおよそ見られないところにある。 |
| 「日本のカラクリ」 田原総一朗 朝日新聞社 01年5月完読 |
日本の政治・経済はもとより、今、問題とされている日本の抱える様々 な局面に関して、非常に分かりやすく著している。歯に衣着せぬ田原 なので、辛らつな部分も多い。しかし、ただ過激な発言で注目を集める ことが目的ではなく、きちんと筋は通されていると思う。彼の思想には 共感すべき点がたくさんあり、鋭い視点には尊敬の念すら感じている。 田原の著書にはしばらくはまりそうである。 |
| 「考える力」をつける本 出口 汪 三笠書房 01年4月完読 |
予備校の講師による執筆なので、おもには受験生向けの内容となって いる。その論理的な思考力に定評があるだけに、「なるほど」と納得さ せられることも多い。しかし、出口氏の頭脳が明晰すぎるのであろう。 私にとって、難解な箇所も多々あり、後半は少々飽きてしまった。ただ、 必要な部分だけをピックアップしていけば、表題どおり、「考える力」を 実際に養うことができそうである。 |
| 「歴史と風土」 司馬遼太郎 文春文庫 01年4月完読 |
司馬が日本と日本人、また近隣アジア諸国を語るエッセイ集。ここに、 ストレートな司馬の考え、思想を見ることができる。その点では、価値 もあるのだが、しかし、正直なところ、歴史小説の方が断然おもしろい し、そこに垣間見える司馬の想いを見つけ出す楽しみもある。ただし、 自身の書き下ろした小説の舞台裏などに言及するものもあるので、そ こは興味深く読んだ。司馬の永遠の命題であった(ように思われる) 仏教の話となると、私には知識も興味もないので、飛ばしてしまった。 |
| 「ペルシャの幻術師」 司馬遼太郎 文春文庫 01年4月完読 |
何と司馬遼太郎の処女作が、文庫本として初登場。今までは、全集で しか読めないものであったので、手にしたときは感動ものであった。昭 和31年に、初めて「司馬遼太郎」のペンネームで執筆され、第8回講談 倶楽部賞を受賞した作品でもある。舞台はペルシャ、モンゴルの王 ボルトルとペルシャの幻術師アッサムとの戦いを描く。戦国・幕末の イメージが強い司馬作品の中ではやはり、異質に感じざるを得ない。 しかし、舞台は違えど、司馬の原点はこの中に十分感じられる。 |
| 「翔ぶが如く 1〜10」 司馬遼太郎 文春文庫 01年2月完読 |
明治維新後の大久保利通と西郷隆盛の確執を描いた長編小説。実は、 この小説を初めて読んだのは、学生の頃。当時は、1巻を読み始めた ところで早々に「おもしろくない」と感じ、闇に葬ってしまった。幕末には 異常なほど興味をもっていたのであるが、その後(明治維新)はどうも 苦手だったせいでもある。司馬作品を途中で投げ出したのは、最初で 最後である。しかし、この年になってようやく10巻まで読みきることがで きたわけであるが、西郷隆盛という男がますますミステリアスに感じら れた。一方の大久保利通は、正直、見直してしまった。 |