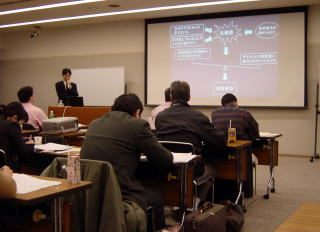トップページへもどる


2003年3月29日 「春の院長日誌スペシャル! 今週の日誌は豪華2本立て」
その1 「謎の肺炎SARS、宮崎医院にあらわる?」
3月某日、そろそろ本日の診療も終わりという夕刻でした。受付のスタッフから「外国人の旅行者がカゼをひいたので診察してほしいという電話です。英語しか話せないそうですがよろしいですか?」との連絡。宮崎医院はグローバルな医療機関をめざしているので、英語はダメなどと言ってはいけません。外国人の患者さんが来院された時にそなえて、当院のスタッフの名札は日英2カ国語の表示となっています。ついにそれが役に立つときがきたか。院長としては「どうぞ、すぐに来院してくださいと伝えて」とキッパリ答えるべきです。

<宮崎医院スタッフの名札は、ドクター、ナースとも日英2カ国語の表記。ASKULで作ってもらいました。>
英語で患者さんとコミュニケーションをとることは大変です。わたしは大勢の外国人の患者さんが来院される、聖路加国際病院というところで、医師としての最初のトレーニングを受けたので、ブロークンながらも何とか英語で診察する方法を身につけないわけにはいきませんでした。しかし、ここ数年は英語で診療する機会などまったくなかったので、かなりブルーな気分で患者さんを待っていました。
患者さんが到着され、挨拶が終わるとインタビュー(問診)のはじまりです。英語を母国語とする国のかただったので、わかりやすい英語で助かりましたが、その安堵もつかの間のこと。プライバシー保護のためにくわしいことは書けませんが、なんと、その患者さんは「2日前まで商用でアジアの某所にいた」、「発熱、息切れ、筋肉痛などが強い」とおっしゃるです。わたしの頭のなかには、「謎の肺炎」、「SARS」という不気味な単語が浮上してきました。
マスコミの大々的な報道によりご存じと思いますが、香港やベトナムを中心として、世界各地でいまだに病原体不明の、謎の肺炎が流行しています。「重症急性呼吸器症候群(略称SARS)」と名付けられたように、急激に重症な肺炎、呼吸不全が進行し死に至る恐ろしい病気で、この病気に罹患したひとと接触した家族や医療従事者にも感染は拡大しています。
怪しい病気の報道さえなければ、この患者さんもただの「旅行者のカゼ」ですむわけですが、病歴や症状からはSARSを完全に否定することはできません。念入りに診察して、胸部のレントゲン写真をとったところ幸い肺炎はなし。謎の肺炎の可能性は極めて低いと思いましたが、大事をとって呼吸器病の専門家のいる総合病院をご紹介して、緊急で精密検査をしてもらいました。その結果も「呼吸器病の専門家がみても肺炎はなく、SARSではない」というご返事で、スタッフともども、やれやれと胸をなでおろした次第です。
いまや、吉良町といえども世界の各地とつながっていて、人や物の動きがあるわけで、グローバルな医療機関となるためには、国際的な保健医療情報に目を光らせておく必要があること、国際社会の公用語である英語によるコミュニケーション・スキルを研いておくことの重要性を身にしみて感じた出来事でした。
その2 「もっと知りたい白血病治療 増刷決定! 夢の印税生活?」
テレビをつければ、米英とイラクの戦争に関する血なまぐさい映像ばかりが目につき、桜が咲いてお花見の季節だというのに、何となく暗いムードが蔓延している毎日です。そんな気分を吹き飛ばすような、明るいニュースはないかいなとパソコンをひらいたところ、わたし個人だけがうれしくなる内容のメールが届いていました。
「ご無沙汰しています。先生にはその後お変わりございませんでしょうか。 さて、この度、おかげさまで初刷が品切れ近くになりましたので、2000部増刷させていただきたくお願いいたします。出版 して1年で2,500部売れましたので大変好調と存じます。」このメールは、わたしの初めての著書である、「もっと知りたい白血病治療」を出版してくれた、医学書院の担当編集者Yさんから届いたものでした。
わたしの本は昨年2月に刊行されたものですが、医学書院が決めた初刷は3000部であり、この部数は(商業的な出版ではない)医学専門書としては多いほうだということでした。出版業界は不況のどん底と聞いていたので、せっかく本を出してもらっても、まったく売れないという事態になれば、出版社に迷惑をかけてしまうことになると心配しておりました。しかし、何かものを作って、お客さんに商品として販売するということは、医者という職業のわたしには経験のない仕事です。今回は「本」という商品を作ったので、読者というお客さんに売らねばならぬというわけですが、どうやったら売れるのか見当がつきません。
大学病院でわたしがかかわった白血病の患者さんやご家族のみなさんには、「本を書いたぞ」と宣伝して買っていただきましたし、白血病の治療薬を製造している製薬会社にお願いして、社員の研修用にと購入していただいたぐらいで、わたし個人のルートで売りさばくには限界があります。学会に出席した時は、まっさきに書籍の展示即売のコーナーに駆けつけ、店員さんの目を盗んで自分の本をなるべく目立つ場所に移動させてみたりしました。そのコーナーでしばらく見張っていると、わたしの本を長時間立ち読みして、けっきょく買わずに立ち去るひとがあるかと思えば、ちらっと眺めただけですぐに買ってくれたひともあり、かなりドキドキの時間をすごすことができます。名古屋市内の大型書店を回ってみても、たくさんおいてある店と、まったくおいてない店があるわけです。(名駅JRタワーズの三省堂書店さん、いつもたくさんならべてくださって、ありがとう!)
そんなわけで、著者自身はどの程度売れているか把握できずに不安に思っていたのですが、1年で2500部も売れてくれて、おまけにさらに2000部の増刷という知らせは、大変うれしいと同時に、著者としての責任も重く感じています。日野原先生や飯島愛ちゃんの本のようなベストセラーになれば、夢の印税生活をおくることもできるかも?(5000部程度じゃ無理だね・・・)
3月15日、16日に名古屋市内で開催された、「家庭医の生涯教育のためのワークショップ」に参加してきました。
「家庭医」という言葉はなじみがうすいかもしれませんが、家庭内や地域で発生した、健康に関するあらゆる問題の解決にあたる第一線の臨床医という意味で、アメリカの医科大学には家庭医を養成する専門のコースや、家庭医療を研究する講座があるのが普通です。日本では、専門に片寄った医学教育はすすんでいますが、家庭医の養成や家庭医療学の研究はおくれており、このワークショップを主催している日本家庭医療学会が唯一の団体です。
「ワークショップ」は単なる講義や講習ではなく、参加者が小グループを組んで、講師から与えられた課題を短時間のうちに討議したり、発表したりする形式の学習会なので、2日間は頭や体をフルに活動させねばならず、つかれましたが、大変に有意義でした。今回のワークショップのテーマは「けんしん」であり、職場や地域での検診の意義、がん検診の是非、各検診項目の解釈、検診後の生活指導の実践方法などについて、全国各地から集まった大学の教員、開業医、勤務医、研修医など幅広い層の参加者が真剣に討議しました。
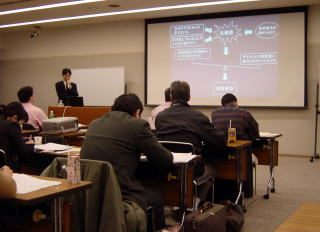
このワークショプに参加している開業医の先生たちは、非常に熱心に家庭医療を実践されているばかりでなく、自分の日常診療のレベルの向上や、自分の診療所が提供できる医療サービスの質の向上のために、常に勉強する努力を怠らないかたたちばかりで、日本の家庭医の精鋭は世界的な水準でみても恥ずかしくないことがわかりました。わたしはまだ家庭医としては一年生ですが、よき先輩がたをモデルにして、研鑽を重ねる必要性を強く感じた2日間でした。
2003年3月11日 「第2駐車場が完成」
宮崎医院の敷地内北西に第2駐車場が完成しました。1月の日誌でご報告したように、旧宅を取り壊して新たに駐車場として造成しました。現在は主に職員用の駐車場として使用しておりますが、医院前の駐車スペースが満車の場合は、患者様の車を数台駐車できるようになっておりますので、ぜひご利用ください。場所がご不明なかたは、お気軽にスタッフにお聞きください。


「過去の院長日誌を読む」へもどる

トップページへもどる