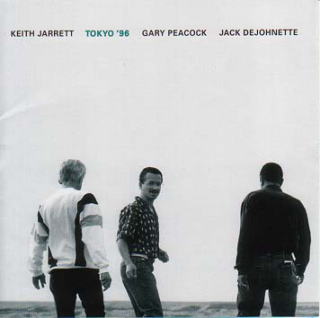トップページへもどる


クイズ: 下の写真は1964年10月10日に撮影されました。この家族はいったいなにをやっているのでしょう?


正解: 「東京オリンピックの開催を祝って、日の丸をあげている!」
この写真は、宮崎家の古いアルバムに貼られているものです。むかし、うちの庭には、写真のような「国旗掲揚塔」が存在しており、お正月や国民の祝日になると、日の丸を掲げていました。東京オリンピックの開会式が行われた1964年10月10日も、父の発案により、一家そろって国旗掲揚、記念撮影となったようで、この写真が残されているわけですね。右の写真で父に抱っこされているのがわたしです。当時2歳11ヶ月ですから、この日のことは、まったく記憶に残っていません。
「東京オリンピック」は、「伊勢湾台風」や「大阪万博」などとならんで、それを体験し、記憶しているかどうかで、年齢や世代がわかる大イベントです。わたし自身を例にとると、大阪万博のときは小学生でしたので、元「万博少年」として、その思い出を熱く語ることができますが、伊勢湾台風が来たときには、まだ生まれていませんし、東京オリンピックはまったく覚えておりません。浪人を重ねて大学に入学した同級生から、あるとき、「ぼくは東京オリンピックの開会式のスタンドで旗を振っていたんだ」という話を聞いたとき、年齢としては数年しか違わないのに、このひとは随分と「おじさん」なんだと、強く感じたことがありました。
東京オリンピックの開催に合わせて、東海道新幹線や名神高速道路が整備されて、日本の社会や街の姿が大きく変貌したことは、よく知られています。貧しいながらも、奥床しい美徳に満ちていた古い日本の姿を知らず、高度経済成長、日本列島改造とともに年齢を重ねてきたのが、わたしたち1960年以降に生まれてきた世代なのです。40年の歳月が経過
して、分別のある大人になったはずのわたしたちは、本当の意味での「豊かさ」を手に入れたのでしょうか?大阪万博で「未来の夢」として描かれていた、携帯電話やパソコンに囲まれた生活をおくっていますが、便利さとは裏腹に、日々のストレスは増していくばかりではありませんか。
アテネで開かれているオリンピックも幕を閉じようとしています。日本人がアテネで獲得した金メダルの数は、東京オリンピックをしのぐ勢いであるとのこと。もし、父が生きていたら、たいそう喜んで日の丸を掲揚したくなったのではないかと想像します。わたしの父は、決して右翼や国粋主義者ではありませんでしたが、なぜ自宅の庭に「国旗掲揚塔」を作ってしまったのか?よその家の庭には、そんなものはありませんでしたから、幼いころから不思議に思っておりました。おそらく、スルスルと旗を揚げる行為や、空高くたなびく日の丸を下からながめることが、ただ単純に好きだっただけではないかと思います。「Show
the flag」と小泉総理につめよったブッシュ大統領や、「For the flag」を五輪野球チームのスローガンにした長島茂雄監督も、父と同類の「旗好き」である可能性が高いですね。その「国旗掲揚塔」も、道路の拡張工事のため、庭の一部が町に接収されたときに、残念ながら取り壊されてしまいました。しかし、モノクロームの写真のなかでは、晴れわたる青空の下で、永遠に日の丸を掲げつづけているのです。

<東京オリンピックの開会に興奮して、ポールによじ登る院長(もうすぐ3歳)>
2004年8月20日 「ネガティブなラベルを貼られると・・・」
わたしたちの町では、例年6月末から7月のはじめにかけて、住民のための検診が行われます。その結果の説明会が、8月上旬に開かれるために、今月は住民検診で異常を指摘された患者さんがたくさん来院されました。もちろん、検診を受けたために、重大な病気が見つかったという場合もありますが、多くの人々は軽い検査値の異常のみで、「心配ありませんよ」と説明すると、みなさんほっとされるようです。
検診の結果を知ることによって、受診者は様々な心理的影響を受けることが知られており、これを「ラベリング効果」と呼びます。検診の結果が正常であったことを知ると、「健康」というラベルが自分に貼られたと感じて、仕事や日常生活の活力が増す人がいます。このように、検診の結果が受診者の心理面によい影響をもたらすことが、「陽性のラベリング効果」であり、検診を受ける効用のひとつにあげられるでしょう。反対に、検診後に「要精密検査」という判定を聞いただけで、「自分はがんではないか」と心配して、大きなストレスを感じる人もあります。こちらは、「健康ではない」というラベルが貼られたと感じて、元気がなくなってしまうので、「陰性のラベリング効果」ということになり、検診に伴う不利益のひとつに数えられます。脳ドックを受けたら、小さな動脈瘤が発見されてしまって、医者は経過観察するだけで良いと言っているが、自分はいつそれが破裂するのか心配になり、夜も眠れないというようなパターンが、典型的な「陰性のラベリング効果」ですね。
検診に従事する関係者は、その結果が受診者に精神的負担をもたらすものであることを、よく知っておくべきでしょう。精密検査が必要と判定されても、すべての人が、がんなどの重大な病気を持っているとは限らないということを、ていねいに説明しなければいけません。さらに、精密検査に対する不安を取り除くような働きかけも大切だと思います。また、「要精密検査」の通知から精密検査実施までの期間や、精密検査の結果を聞くまでの期間を、できるだけ短くする努力が必要です。これは、受診者が不安を持って生活する時間を最小限にとどめるための措置となります。
これまで地域や職域で実施されてきた検診の内容について、最近では「科学的根拠に基づいた医学(Evidence
Based Medicine)」の手法を用いた、批判的吟味が加えられるようになってきました。その代表的な報告として、「米国予防サービス特別委員会
(U.S. Preventive Services Task Force) による勧告」というのがあります。そこで、「生命予後を改善し、益が害より多いという良質な証拠があるため、該当者への定期的な施行を推薦する」と勧告された検診の項目は、血圧、身長・体重、血清総コレステロールおよびHDLコレステロール(対象:35歳以上の男性、45歳以上の女性)、子宮頸部細胞診検査(女性)、便潜血・S状結腸鏡による大腸がん検診(50歳以上の男女)、乳腺撮影による乳がん検診(40歳以上の女性)、骨密度(65歳以上の女性)だけです。それ以外の検査は、厳密な検討を加えてみると、病気の予防や早期発見には役立たないものばかりであることがわかりました。たとえば、わが国の検診で必ず行われる「胸部レントゲン写真」については、肺がん検診に用いた場合ですが、「効果がないか、害が益より多いといういくつかの公正な証拠がある」として、「症状のない人への定期的な施行を反対する」という勧告が、アメリカでは出されているのです。
つまり、日本の集団検診における検査項目は、科学的根拠に基づいて採用されたわけではなく、慣習に基づき(?)、役所や検診会社により、恣意的に選択されたものなのです。先にご紹介した子宮がんに対する子宮頸部細胞診や、大腸がんに対する便潜血などの検査を除けば、毎年検診を受けつづけていても、病気(特にがん)の早期発見につながるとか、長生きができるという、科学的な証拠は(今のところ)ありません。その程度の効用しかない検診の結果に翻弄されて、自分が「健康ではない」とか、「病気である」というネガティブなラベルを貼られた気分となり、不安な気持ちのなかで生活することは、とてもつまらないことです。受診者の不安な気持ちにつけこんで、検診後に過剰な精密検査を行って、多大な利益をあげている医療機関が存在するのも問題です。
もし、検診の結果で、ご心配なことがあれば、そのデータを持って当院までお出かけください。検診を受けられたことが、決して不利益にならないように、あなたのデータを解釈して、安心と納得が得られるように、「本音」でご説明いたします。ネガティブなラベルをはがして、すっきりとした気分でお帰りいただけますように。 (← ほぉ~、めずらしく「院長日誌」内で、宮崎医院の営業活動をしているみたい。)

<お盆休みに町内某所で咲きほこるヒマワリの大群を発見。
慣れないケータイのカメラで撮影したのでピンボケで失礼!>
キース・ジャレットのCD「TOKYO '96」を聴く。このCDは1996年3月30日に、東京のオーチャード・ホールで開かれたコンサートのライブ盤で、キース・ジャレット(ピアノ)、ゲイリー・ピーコック(ベース)、ジャック・ディジョネット(ドラム)によるトリオの演奏がおさめられています。なぜ、これを久しぶりに引っ張り出してきて聴く気になったか?それは、この日のコンサートに、皇太子殿下と雅子妃殿下が、ご臨席されていたことを思い出したからです。
ご成婚のときに紹介された雅子様のプロフィールに、好きな音楽家として、バッハやラフマニノフとともに、キース・ジャレットの名前が上げられていました。キースを日本に呼んでいるプロモーターの鯉沼氏が、それに感銘を受けて、この日のコンサートに皇太子殿下ご夫妻をご招待したのです。鯉沼氏は、「これは、日本初の皇太子ご夫妻をお迎えしての、ジャズ・コンサートの歴史的ドキュメント」であると、ライナー・ノートの冒頭に記しています。そして、良い意味での緊張感が、音楽家たちに生まれたようで、この日の演奏はすばらしいものとなりました。
報道によれば、体調を崩された雅子様のご病気を、宮内庁は「不安や抑うつ状態を伴った適応障害」と発表したそうです。「適応障害」という病名は、なじみが薄いので、わたしも幾人かのひとから、「どんな病気?」と質問を受けました。ひとの心を扱う、精神科領域の病気は「診断」がむずかしく、同じ患者さんを複数の精神科医が診察しても、病名がなかなか一致しないことがあります。ある医者は「うつ病」と言い、別な医者は「神経症」と言うといった問題が発生するわけです。このような混乱をさけるために、世界中の精神科医たちは、米国精神医学会が作成した「DSM
(Diagnostic and Statistical Manual)」と呼ばれる、統一されたマニュアルに沿うかたちで、病気の診断や分類を行っているのです。このマニュアルの最新版は、1994年に改訂された第4版であることから、「DSM-Ⅳ」というのですが、今回の「適応障害」という病名は、「DSM-Ⅳ」に基づいてつけられたものと推測できます。
マクドナルドやディズニーランドの接客マニュアルに象徴されるように、アメリカ人がマニュアルを作ると、非常に親切丁寧ではあるのですが、客観性や再現性を重視するあまりに、内容や手順が煩雑になりすぎるという欠点があるようです。「DSM-Ⅳ」もアメリカから直輸入したマニュアルなので、病名だけを取りあげても、「身体表現性障害」、「全般性不安障害」などといった、訳語をみただけでは、どんな病気か判じがたい、奇っ怪な述語に満ちており、専門家以外には(もしかしたら専門家にとっても?)、大変扱いにくいものだと、わたし自身は感じています。
それでは、「DSM-Ⅳ」に記載されている「適応障害」の診断基準を読んでみましょう。「ストレスを引き起こす出来事に反応して、その出来事の発生から3ヶ月以内に、情緒的、または、身体的な症状が現れる」、「そのストレスを引き起こす出来事にさらされると、予想を超えた著しい苦痛を感じる」、「社会、職場、学校において、自分の役目を果たすことに支障を来す」というのが、その主な内容です。わたしのような一般内科医が、「適応障害」という病名を聞いて即座に思い浮かべるのは、「職場の配置転換により、これまでの業務内容とは全く異なる仕事を強いられて、そのストレスから出社できなくなってしまった会社員」というような患者さんです。あるいは、「国際結婚により、文化や風土の異なる外国での生活を余儀なくされ、緊張やストレスから情緒が不安定になった主婦」というのも、「適応障害」の典型であると思います。
皇太子ご夫妻が客席で耳を傾けていらっしゃった、キース・ジャレットのコンサートは、
"It could happen to you" という曲からはじまります。この曲はジャズのスタンダート・ナンバーのひとつですが、原曲の歌詞をみると、「そんなことは誰にだって、あなたにだって起きること」と歌われています。何が起きるのかというと、それは「恋に落ちる」ことであり、ふとしたきっかけから恋に落ちるのは、誰にだって起きる、あなたにだって起きること、という内容の歌です。わたしは、このコンサートのオープニングを飾る演奏を聴いているうちに、「恋」だけではなく、「心の病い」も、誰にだって、「あなたにだって起きること」なんだという思いを強くしました。
実はこの1996年の公演からほどなくして、キースは「慢性疲労症候群」という難病にとりつかれ、一時はまったくピアノが弾けなくなり、ジャズの表舞台から消えました。再起不能の噂が流れている間も、彼は闘病やリハビリを続けて、1999年に「メロディ・アット・ナイト、ウィズ・ユー」というアルバムをリリースし、みごと復活したのです。この復帰第1作のCDは、自宅のプライベート・スタジオで録音されたソロ・ピアノ集であり、どのナンバーも穏やかな美しさに満ちています。もし、わたしが雅子様の主治医であれば、ストレスに対する治療のために、このCDをぜひ処方してさしあげたい。そして、難病を克服したピアニストの音楽の力で、再び皇太子殿下とともに、彼のコンサートにお出かけできるまでに回復されることを願ってやみません。
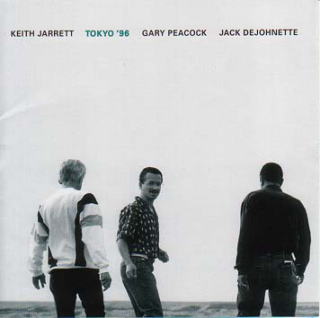
<真ん中の久米宏みたいなおじさんがキース・ジャレット。
このライブはDVDにもなっております。>

「過去の院長日誌を読む」へもどる

トップページへもどる