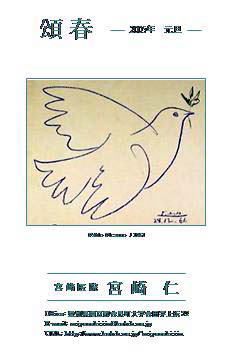トップページへもどる


<みずからの感情を語ることは、ある意味では看護婦としての「恥」をさらすことのように感じられるかもしれません。逆に、おおっぴらに語るにはあまりにもくだらなく思えることもあります。けれども、感情の問題をくだらないと感じることから問題にしなければなりません。それは、看護婦が人間として大事にされていないということでもあります。(中略)最近しばしば新聞をにぎわせている医療事故や看護婦による犯罪にしても、その裏側には、軽んじられ、無視されてきた感情が、語られないままに渦巻いているのではないでしょうか。>(武井麻子「感情と看護:人とのかかわりを職業とすることの意義」)
どうも「ムカつく」という言葉は、世代によって受けとるイメージが、ずいぶんと異なるようなので、「新解さん」こと「新明解国語辞典」(わたしの手元にあるのは第5版)で、「むかつく」という言葉をひいてみました。①「胃の中の物を吐きそうな感じがする」、②「今にも声(言葉)に出して怒りたくなる」、というふたつの語義がこの辞書には書かれています。①はもともとの意味であり、用例として「胸がむかつく」という文がのっていますが、この場合の「むか」は、ひらがなで表記されるのが普通です。問題となっている「医者ムカ」の「ムカ」は、もちろん②の意味ですね。それにしても、さすがは新解さん、「今にも声(言葉)に出して怒りたくなる」という語釈のうまさには脱帽しました。「ムカつく」という言葉が、はげしい怒りに到達する途上(直前?)の感情をあらわしていることを的確に説明しています。この怒りがさらに高まって爆発する(「キレる」)方向にむかうのか、そのまま胸のなかにストンとおさまってしまうのかが判然としない、非常に不安定な感情を「ムカつく」という言葉で表現しているわけで、「ムカ」をカタカナ表記にすると、そのニュアンスはさらに強調されると思います。
これまで各自の胸のなかに封印されてきた医師たちの「感情体験」が、「ムカつく」という言葉に触発されたあげく、その封印を破ってメーリングリストのなかで生々しく語られることになりました。自らの感情を語るのは、「恥」であり「くだらないこと」であるとする「病棟文化」のなかで育ってきたのは看護婦も医者も同じです。わたしたち医療者は、自らの感情について包みかくさずに語ることには、まだ慣れていません。しかし、診療の現場では、患者さんが傷つくこともあれば、治療者である医者が傷つくこともあるのです。最近では「医者が人間として大事にされていない」という状況に遭遇するのもめずらしくはありません。今回のTFCにおける討議でも、患者さんに殴られた、つきそいの家族に首をしめられたといった事例がいろいろと報告されています。武井麻子先生が「感情と看護」で指摘されたように、「医療事故の裏側には、軽んじられ、無視されてきた感情が、語られないままに渦巻いている」というのは、まったく本当のことです。
それでは、「医者ムカ」問題を解決するにはどうすればよいか? ある先生は「現場で葛藤を生じた事例を集め、様々な立場から忌憚のない意見を戦わせる」という方法を提言されています。武井先生の本のなかにも、「自らの感情に気づく作業は一人ではできません。誰かの力を借りる必要があります」と書かれています。まだ感情労働に慣れていなかった研修医のころを思い出してみても、「医者ムカ」状態となった自分の感情を正常に戻すには、先輩のレジデントや、病棟での「戦友」である新人ナースとの「語らいの時間」がぜひとも必要でした。TFCのように感情面の配慮まで行き届いた集団であれば、メーリングリストでのやりとりのなかで、ムカついている自分を客観的に見つめなおすという作業もできる時代です。いずれにせよ、傷つかずに医業をすることは不可能なわけですから、ネガティブな感情体験をくすぶらせたままにしないで、誰かに「語る」という行為は大変重要な意味があるのではないでしょうか。
さて、TFCにおける「医者ムカ」の反響には、思わぬオマケがついてきました。多数のTFC会員のみなさまが、「医者ムカ」の原著(?)を読むために、宮崎医院のホームページにアクセスされたようですが、「院長日誌」のみならず、「宮崎医院の歴史」にも深い関心をお寄せいただきまして、開院時の宣伝ビラのことまでが話題の俎上にあがってしまいました。三代目院長であるわたしは、これまで宮崎医院開院時の標榜科目は「外科・耳鼻科・内科・皮膚科」であると信じていましたが、TFC主宰の田坂先生から、宣伝ビラの写真をよく見ると、「皮膚科」ではなく「皮梅科」となっているとのご指摘を受けました。なるほど、見直してみると、たしかに「皮梅科」だ! 「皮梅科」とは皮膚科・梅毒科の略称だと思いますが、「花柳病」という言葉がしっかりと生きていた、太平洋戦争前の古き日本社会の雰囲気を色濃く伝える診療科の名前ですね。自分で宣伝ビラのデジカメ写真を撮って、ホームページにアップしていながら、これまで全く気がついておりませんでした。田坂先生、TFC会員のみなさま、ありがとうございました。

わかりにくい写真で恐縮ですが、
「あめ」と「お水」です
★
今年も町主催の「禁煙教室」で
漫談を披露してきました
★
受講者のみなさまは、
タバコが吸えないので、
ソワソワ、イライラしちゃうかも・・・
★
そこで、キャンディとドリンクは、
「禁煙教室」の必需品なのです
保健師さんたちが新聞の広告で折った
キャンディボックスがシブイ!
★
2004年2月2日:吉良町保健センターにて撮影
TFC(Total Family Care)は、広島市の開業医である田坂佳千(たさかよしかず)先生が主宰されている医療系メーリングリストです。国内外に散らばる1600人以上の医師・医学生が会員となっており、「家庭医」「プライマリ・ケア」「開業医」をキーワードとして、あらゆる医学医療に関する話題が連日ホットに議論されております。わたしも、開業医になってからTFCの仲間に入れていただきましたが、毎日配信されてくるメールを読んでいるだけで、臨床医としてのレベルが着実にアップする、本当にすばらしいメーリングリストだと思います。宮崎医院の外来診療も、もはやTFC経由の情報なしでは成り立たないと言っても過言ではありません。そのTFCにむけて、1月29日付け「院長日誌」とほぼ同じ内容の文章を、「医者がムカついてはダメですか? ~「感情」と「医業」~」というタイトルで投稿してみました。田坂先生によるTFC運営のポリシーは、<「なごやかに」しかし「本音」で議論を深めること>。拙文「医者がムカついてはダメですか?」(略して「医者ムカ」)を読んで、「家庭医マインド」にあふれるTFC会員のみなさまがたから、どんな「本音」の感想が寄せられるか、ドキドキしながらレスを待ちました。
「医者がムカついてはダメですか? ムカついてはダメですよ。」
こんな毅然としたコメントを皮切りにして、現在までのところ、13本の感想あるいは関連した話題のメールが、TFCを通じて配信されています。わたしの個人アドレスあてにいただいたメールもあるので、予想した以上の反響におどろいてしまいました。やはり、「感情」と「医業」というテーマは、TFC会員のハートをズドンと刺激するみたいですね。TFCに投稿されたメールは無断で外部に転載できないというルールがあるので、諸先生がたからいただいたコメントをそのままのかたちで、ここにコピーしてご紹介することはできません。そのエッセンスだけを勝手にまとめてみました。
【「医者ムカ」に対するTFC会員からの反響メール・抜粋&要約】
◆医者の感覚が全て正しいわけではなく、むしろ逆である。ムカついている対象の患者さんのほうが「普通の感覚・感情」かも。
◆医者が患者さんに「ムカつく」以上に、患者さんが医者に「ムカついたり」、「傷つけられたり」するほうが、はるかに多いのでは。
◆「医者」以前の問題。社会人として他者へのムカつきや、顧客の悪口をネットで公開することは許されない。
◆医師は社会常識が欠けているので、一般的な常識やマナーをもっと学ぶ必要がある。
◆患者さんの話を聞きながら「こんな人もいる、こんな人生もある」とおもしろがっていれば、ストレスも溜まりにくいのでは?
◆「好奇心」に加えて、「探求心」があれば、何とかやっていける。
◆ムカついていないで、「プロの仕事」(外部から求められているレベルの医師としての仕事)をしようと、「心のスイッチ」を切り替える。
◆どういう相手、どういう状況のときに、自分が感情的になってしまうかを、あらかじめ知っておけば対処しやすいです。
◆「横柄な医者」と「普通の患者」なのか、「普通の医者」と「良識のない患者」なのか? 最終的にはコミュニケーションの問題。
◆「社会性のない患者」に対しては、医師が媚びへつらうことなく毅然とした態度で臨むことが肝要。ただし、「社会性のない患者」というのを、「社会性のない医師」が如何に判断するかが問題。
◆「医師に肉体的、精神的余裕がなくて、患者さんに質の高い、心優しい医療を提供することは困難」ということを、もっと社会にアピールすべきだ。
◆「感情規則」から解き放たれて、情緒的、emotionalな対応も時には必要なのかも。EBM
(Emotional Based Medicine)はだめでしょうか?
◆「感情で気づいて、それを理論で分析して、感情で返す」、それが医療倫理。
「ムカつく」という言葉を、このエッセイのタイトルに採用したのは、もちろん熟考を重ねたあげくの選択なのです。「ムカつく」という挑発的な言葉が、こころ優しきTFC会員を刺激して、「医者ムカ」に関するディスカッションが、にわかに沸騰してしまったみたい・・・ (「医者ムカ」の反響・その2 につづく)

「広報きら」2月号に院長登場!
★
1月21日の「日誌」に書いた
「30年前の作文」に関する取材記事です
(こんなにデカく載るとは思わなかった・・・)
★
町内全世帯に配布されちゃったので、
患者さんたちから「広報見たよ」って
毎日言われています
★
記事の全文はこちら
厚生労働省は2月4日、今季の「インフルエンザ流行入り」を宣言しました。これは、過去10年間で2番目に遅いとのこと。また、流行シーズンに入ったとはいえ、累計の患者数は、昨年の同じ時期に比べて8分の1以下なのだそうです。ニュースでもお知らせしましたように、宮崎医院では1月11日に今季の第1号患者さんを診断。その後も患者さんの発生は切れ目なくつづいており、特に先週からは「流行シーズン突入!」を実感できるほどの混雑ぶりになってきました。
当院における今シーズンの特徴は、ほとんどの患者さんがB型インフルエンザであることです。インフルエンザウイルスにはA型とB型があり、流行期は大部分がA型の感染というのが通常のパターンで、B型は時期はずれに数例出現するだけなのが普通です。ところが、今年はなぜかB型の感染ばかり。こんなに多くのB型インフルエンザを診療したのは、はじめての経験と言ってもよいでしょう。
インフルエンザの流行が遅れるシーズンには、B型の感染が多くなるそうですが、さすがにこれは異例の事態。宮崎医院の近隣の事情を説明すると、1月9日、10日の連休明けから、Y小学校2年生のクラスでB型インフルエンザがアウトブレークしました。その後、その小学校を中心にピンポイントな流行がつづき、そろそろ終焉かと思ったのです。ところが、厳寒の1月30日に町内こども会連合による合同マラソン大会が開催され、それに参加した児童がつぎつぎにB型インフルエンザに感染してしまい、Y小学校の学区外にも感染は拡大。B型インフルエンザという感染症が町内に持ちこまれて、小学生を中心にしてどんどんと広まる様子が、診察室に居ながらにして時々刻々と観察できたわけです。
東南アジア、特に香港でのサーズ(SARS)感染拡大の元凶として、「スーパースプレッダー」と呼ばれるひとたちの存在が知られています。「スーパースプレッダー」は、体内に大量のウイルスを保有して、よくセキをする。そのために、平均的なサーズ感染者と比べて、より多くのひとにウイルスをばらまくのです。今回の当地区でのB型インフルエンザの流行には、Y小学校2年生のクラスと、町内こども会マラソン大会の参加者のなかに、B型インフルエンザウイルスの「スーパースプレッダー」が存在したのではないかと、わたしは推理しております。
B型インフルエンザばっかり、毎日何人も診察していると、A型とのちがいに気がつきます。まず、症状はA型よりも地味。発熱は38℃をこえない場合もまれではなく、セキや鼻水も軽い印象です。ところが、これらの症状がダラダラとしつこく持続する。また、インフルエンザの治療薬である「タミフル」の効果も、切れ味がいまひとつといった感じ。これまでよく診てきたA型インフルエンザ感染では、セキなどの症状はハデで熱も高いのですが、「タミフル」を処方すると1~2日で劇的に改善しました。ところが、B型インフルエンザの感染では少し様子がちがうようです。5~7日も熱などの症状がすっきりとしないパターンが多いから困っています。このほかにも、なぜか、家族内での感染拡大はA型よりも頻度が低いとか、典型的なインフルエンザ症状がそろっているのに、迅速診断キットでは陽性にならないなど、不思議な現象が多々あります。昨年末にせっせと注射した、ワクチン接種による予防効果も疑問あり? はっきりいうと、「B型インフルエンザって、変なヤツ」。
わたしたち内科系開業医にとって、インフルエンザの流行期は年間を通じて最も多忙な季節。「土用の丑」におけるウナギ屋さんや、クリスマスにおけるケーキ屋さんのようなものです。それなりの気合いをいれてはたらいておりますが、連日連夜、おかしなB型インフルエンザばかりを相手に闘っていると、そろそろしんどくなってきました。なにしろ、拙者の血液型も、熱しやすくさめやすい「B型」で・す・か・ら。切腹~。

このひとはインフルエンザの治療薬である「タミフル」の宣伝キャラクター
★
名前は「たみちゃん」です。(こんなベタなネーミングで大丈夫か、中○製薬!)
★
たみちゃん、B型には少し弱いみたい・・・
1月14日のYahoo!ニュースで、<医師がHPで患者を中傷 「頭悪い、二度と来るな」>というヘッドラインを見つけてびっくり。共同通信の記事によれば、水戸市の病院で耳鼻科の勤務医をしている28歳の女性が、自分のホームページの日記コーナーに、患者さんとのやりとりや、手術の様子を書きこんで、「頭が悪い」、「今すぐ帰れ。二度と来るな」などと、匿名ではあるものの患者さんを中傷する内容を公表していたとのことです。さらに、忘年会中に呼び出された緊急手術について、「この緊張感がたまらない」と書いていたことも問題視されています。昨年12月下旬に勤務先の病院に情報提供があり、ホームページは閉鎖され、この医師は病院から解雇されてしまいました。
医師のホームページ、日記コーナーといえば、この「院長日誌」もまったく同じジャンルではありませんか。そこに書きこむ内容の選択や、表現の方法については、十分配慮しているつもりですが、自分が意図せぬところで、読むひとのこころを傷つけてしまうリスクもあり、本当に「明日はわが身か?」と身震いするようなニュースでした。「院長日誌」愛読者のみなさまにおかれましても、「こいつ、変なこと書いているぞ」と思われましたならば、ただちにご指摘、ご注意くださいますように、謹んでお願い申し上げます。最近では、簡単に更新できるブログの流行もあり、日記を日々公開している医者も大勢いるのですが、誰でも気軽に書きこめるし読めるという利便性のウラで、今回の報道のような、憂慮すべき事態もたくさん発生しているということでしょうか。
この事件をおこした女医さんは、職場で患者さんを診察していてムカついたので、それをバカ正直に書きこんでしまった。医者だって人間ですから、仕事をしていてムカつくことはあります。いわゆる「むずかしい患者 (difficult patient)」と対峙すれば、相手から自分の感情を傷つけられることも、まれではないのです。しかし、医療職はあくまでも「対人サービス業」ですから、「わたし、ムカついてます」ということを、直接的な方法で相手に示すことは禁じられています。われわれは、患者さんを前にして、怒ったり、どなったり、泣き出したりしてはいけないという、職場の「感情規則」にしばられているのです。どんな修羅場に立ち会ったとしても、感情的にはほとんど動ずることなく、冷静沈着に、自分の仕事をてきぱきとこなすことができる人間になりなさいと教えられてきました。「内科の神様」である、かのウィリアム・オスラー博士も、医師にとって必要な精神的な資質とは、「平静の心 aequanimitas」であると断言されております。
医療サービスの従事者、特にナースは、患者さんから発せられた、怒りや不満、時には過剰な好意といった、さまざまな「感情」に常にさらされながら働いています。このように感情が労働の大きな要素となっている仕事を「感情労働」と呼ぶのだということを、「感情と看護:人とのかかわりを職業とすることの意味」という本で知りました。自身もナースである、看護学者の武井麻子さんが、これまで無視されてきたナースの「感情の領域」に注目して、看護という仕事の本質を掘りさげた好著です。この本によると、「感情労働」の特徴とは、①対面あるいは声による人びととの接触が不可欠であること、②他人のなかになんらかの感情変化(感謝の念や安心など)を起こさなければならないこと、③雇用者は、研修や管理体制を通じて労働者の感情活動をある程度支配する、ということだそうです。これらの特徴を満たしているという点では、銀座の高級クラブのホステス嬢や、航空会社の客室乗務員さんと同様に、われわれ医者の仕事も、りっぱな「感情労働」ということになりますね。実際のところ、「雇用者が労働者の感情活動をある程度支配する」仕事だから、ホームページで患者さんを中傷した女医さんも、勤務先の病院をクビになってしまったわけですし。
「感情規則」のために、自らの生々しい怒りを、職場において表出することがゆるされないから、それをグイッと呑みこんで帰宅して、ホームページやブログに「頭悪い、二度と来るな」などと書きこむ。とても、わかりやすい行動ですね。でも、ずいぶんと子供っぽい。「おとな」のお医者さんならどうするでしょう。「おとな」の援助者になりなさいと説く、精神科医の春日武彦先生に相談してみましょうか。春日先生が昨年出版された「援助者必携 はじめての精神科」(医学書院)は、こんなときにとても役に立つガイドブックです。「我々自身の怒り、悔しさ、不快感」という、まさに医療者の「感情」のことを扱った章を読んでみます。人格障害の患者さんに対して「逆ギレ」してしまった自分の経験を語られた後で、<とはいうものの、読者も一度は逆ギレをしてみれば、それによって生ずる後味の悪さや気まずさ、医療者として何とか自己正当化をはかろうとする見苦しい心の揺れなどを実感して、けっきょくは「ムカついても、根気よく冷静沈着なトーンをキープする」ことが自分にとっていちばんストレスが少ないことに気づくだろう。>なんて書いてありますよ。<あまりに失礼だったり粗野な相手に対しては、いわばショック療法的な意味で言い返してやったらどうだろうかと考えたくなる。しかしそれはリスクが大きすぎる。相手が驚いて理性を目覚めさせるといった期待はしないほうがよい。>なるほど、なるほど。<たんに我慢するとか泣き寝入りをするといった文脈でとらえると、我々は相手の態度に対していつまでも恨みを抱いてしまいかねない。我々の仕事とは、つまり分厚い人間図鑑のページをランダムにめくっていくようなものである。(中略)我々は怒りよりも好奇心で向かい合うのが正解なのであろう。>さすが、「おとな」の援助者ですね。
春日先生は別のインタビューでも、<「好奇心」というと、なんか、不謹慎な感じを持つ人もいるみたいですが、そういうのは間違えですよ。だって、笑い物にしているわけじゃないんですから。好奇心というのはまず「その人に関心を向けている」ということです。そしてそのうえで、ある程度距離を置くということ。この2つがそろってはじめて「好奇心」なんです。(中略)好奇心があるというのは援助者としていいことだと僕は思いますね。>と述べていらっしゃいます。わたしもまったく同感。「感情規則」でがんじがらめの職場で、できるだけストレスをためずに、おもしろがって働くには、相手に対する「好奇心」が最大の武器なのです。ちなみに、わたし自身が仕事中にムカついたりキレそうになったときには、頭のなかで慈愛に満ちたオスラー博士のお顔を思い浮かべながら、「平静の心、平静の心、平静の心」いう呪文を唱えることで、自分の感情をクールダウンするという習慣を、研修医のころからつづけております。近ごろムカつくことが多いとぼやいているドクター諸兄も、ぜひおためしあれ。

昨年末にパナソニックの液晶ビデオプロジェクターと60インチのスクリーンを購入。
★
わが6畳の「遊び場」が、小さなホームシアターに変身!
★
休日はウッディ・アレンの古い映画なんかをDVDでみております。
「もしもし、こちら吉良町役場です。先生が30年前に書かれた作文について取材したいのですが」
「エッ、30年前に書いた作文の取材?」
「はい、本年3月で吉良町が誕生して50周年となります。それを記念した町の広報誌を編集中ですが、町制20周年のときに募集した作文コンクールで、先生は町長賞を受賞されていますので、ぜひ当時の思い出などをうかがいたいと思いまして」
「それって、わたしが中学1年生のときに書いた作文のことですか?」
「はい、そうです。」
「賞をいただいたのはおぼえていますが、何しろ30年もむかしのことですから、何を書いたか全く記憶しておりません。思い出を語れと言われましても・・・」
「それでは、当時の広報に掲載された作文のコピーを、これから宮崎医院までお届けしますので、目を通しておいていただけますか?
後日インタビューにうかがいますから。」(ガチャ)
そんなわけで、いまから30年もまえの、1975年(昭和50年)に、当時13歳であったわたしが書いた作文のコピーを、思いがけず手にすることになりました。さらに、家の押入のなかを探してみると、そのときの賞状まで出てきたではありませんか。「海洋都市・吉良町」というタイトルだけは、かろうじておぼえていましたが、改めて読みかえしてみても、「これ、ホントに自分が書いたもの?」って感じ。賞状の文面をみて、「吉良町の未来像を求めて」というテーマで募集された作文だったことも思い出しました。
吉良町は昭和30年3月に、吉田町と横須賀村が合併して誕生した町です。今年は町制50周年にあたり、様々なイベントが企画されているのですが、町の歴史をふりかえる気運のなかで、町制20周年の際に書かれた作文のことを、町役場の誰かが思い出したようです。それで、今回の取材の話が浮上して、古い広報誌のなかから発掘された作文が、30年ぶりに作者であるわたしの手元に戻ってきたという次第。

<役場から届けられた、広報「きら」昭和50年3月号のコピー>
<吉良町といったら何を思い出すかと、他の町の人々に聞いたら、どんな答が返ってくるだろうか。おそらく、「忠臣蔵の吉良公・荒神山の吉良の仁吉・人生劇場の尾崎士郎。」というのではないだろうか。また、他の町の人々ばかりでなく町民までもそういうだろう。はたして、それでいいのだろうか。このような過去の出来事にいりびたっていて、特筆すべき産業もないようではいけないと思う。もっと新しい産業をおこさなければ、吉良町の将来は有望なものとはならないだろう。>
冒頭の段落をここに書き写してみて驚くのは、30年の歳月が経過しても、この町の状況は全く変わっておらず、「町制50周年記念作文・吉良町の未来像」として2005年に提出したとしても、そのままで通用してしまうという事実です。そういえば、町内のあちこちに貼られている町制50周年記念ポスターにも、「吉良の三人衆」として、吉良上野介、仁吉、尾崎士郎のイラストが当然のようにレイアウトされていますね。何年たってもほとんど変化のない町というのは、のんびりとしていて、ある意味では幸福な土地であるとも言えますが・・・
この作文の中味を読むと、吉良町の地理的な特性を活かして、「一大総合海洋レジャーランドを建設せよ」とか、「のりや魚の養殖を研究する試験場をつくれ」とか、高度経済成長時代に育った子供らしい、景気のよい提言に満ちているのです。その一方で、文章の最後に「吉良町の美しい自然も保護せよ」と、環境問題に言及するところに70年代後半という時代の空気を感じます。1975年の日本には、携帯電話も、インターネットも、コンビニも、宅急便もありませんでしたが、まだ「未来」という言葉が輝きを失っていない時代でした。
13歳のときの自分が描いた「未来の吉良町」で、43歳のわたしは毎日生活しているわけです。30年たって、日本も世界も大きく変貌しました。いまの中学生たちが、どんな「未来像」を思い描いているかよくわかりませんが、30年前のわたしの作文のような楽観的なイメージではないでしょうね。大人になったわたしたちに与えられた仕事は、わたしたちにつづく若い世代が安心して生活できるように、吉良町のおだやかな風土を守ってゆくことだと思います。取材のために、宮崎医院を訪問された広報課職員のかたには、そのような趣旨のお話をいたしました。広報担当のかたは、30年前にいただいた賞状をかかえて、ニッコリとほほえむ現在のわたしの写真を撮りたかったようですが、もちろん丁重にお断りしました。しかし、賞状だけは写真に撮って広報に載せたいということで、持ってかれてしまった。みなさん、広報「きら」2月号の記事にご注目くださいませ。

<こんなものが押入の中からすぐに出てくるからこわい>
みなさま、年末年始の休暇はいかがでしたか? お正月と言えば年賀状。暮れに自分から出す分を作るのはわずらわしいのに、年が明けて、ひとからもらったものをながめるのは楽しいですね。わたしも200枚近い年賀状をいただきましたが、本年のベストワンはすぐに決まりました。
艶やかな緋色の振袖を着た若い女性が、気恥ずかしそうな笑顔をカメラにむけている写真。その下には「先生、お元気ですか? 私は見ての通り元気です。今年はいよいよ私も成人式です。私の振袖姿見てください。」という文章がそえられています。彼女は高校入学と同時に、血液の難病におそわれました。治療のために大学病院に入院して、わたしが主治医となったのですが、それから3年もの長きにわたり、治療薬の副作用や骨髄移植の合併症に苦しめられて、本当につらい日々がつづいたのです。しかし、彼女はそれによく耐えて、病気は完治しました。そして、現在では、新しい目標にむかって歩んでいます。成人式をむかえて、彼女自身はもちろんのこと、この写真を撮影している、ご両親のお喜びは察するに余りあります。
完治が困難な病いをあつかう血液内科医の仕事は、労多くして報われることが少ないのですが、振袖を着てほほえんでいる彼女の年賀状を眼にしたら、難病とたたかう医者をやってきて良かったと、素直に喜ぶことができました。彼女以外にも、たくさんの昔の患者さんたちから、「元気です」という年賀状が届いており、このときばかりは主治医冥利につきるというものです。
「仲間と。 がんと向きあう子どもたち」(がんの子供を守る会/フェロー・トゥモロー編、岩崎書店)という本は、「小児がん」の元患児たちが、成長後に子供のころの闘病体験をふりかえって綴った文章が集められています。小児がん経験者が集まって、自分の経験を話したり、悩みを相談したりする親睦会である、「フェロー・トゥモロー」という団体のメンバーが編集、執筆しているのですが、治療者側のわたしにとっては、いろいろと考えさせられる内容でした。
「髪の毛のこととか体の傷とか、大人から見ると、命が助かったんだから、そのくらいはどうでもいいじゃないと思うかもしれないけど、思春期の頃って、気になって、気になって・・・・。大人には分からないのかな。」
「髪の毛も、『あとで生えるんだからいい』って言われたことがあるけど、今が大事だよ。」
「治った人だって、治ればふつうの人と同じ欲がある。もっと欲を持とうよ。『治ったんだからいいじゃない』で止まらないで。」
このような元患児のみなさんの率直な発言を読んでいると、かつてわたし自身も病棟や外来で、「命が助かったんだからいいじゃん」といった言葉を、不用意に投げかけて、患者さんたちを傷つけたり、失望させていたにちがいないと、いまごろになって反省している始末です。
どんな難病でも、それが治れば、患者さんは治った後の人生を生きなければなりません。現在25歳の女性は、3歳のときに急性骨髄性白血病の治療を受けて治癒していますが、いまだに「人に触れられるのが苦手」など、闘病のための心的外傷による症状があると、この本のなかで書いています。わたしたち医者は、これまで必死になって目の前にある病気をやっつける努力を続けてきました。その結果、がんなどの重い病気を克服した人々の数は、どんどん増えています。ところが、治ったあとの元患者さんたちが、どんな気持ちでいるか、どんな問題をかかえて生活しているかということには、まるっきり無関心であり、それこそ「治ったんだからいいじゃん」という態度であったと思います。
やっと最近になって、病気を経験した、あるいは現在も経験中である「当事者」の物語り(ナラティブ)に、積極的に耳を傾けることが重要であることを、われわれ医療者も気がついて、「当事者研究」とか、「ナラティブ・アプローチ」と呼ばれる試みが盛んになりつつあるようです。「フェロー・トゥモロー」のような、当事者である元患児、元患者のみなさんによる自発的な活動も、全国各地で動きだしています。開業医となった、いまのわたしにできることは、自分が担当した元患者さんたちの「サポーター」として、「治ってからの人生」を見守りつづけることだけです。今年一番うれしかった「振袖の年賀状」をながめながら、そんなふうに思いました。
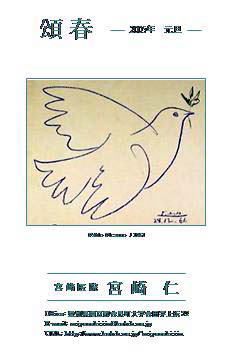
<わたしの年賀状はパブロ・ピカソが描いた鳩の線画です>

「過去の院長日誌を読む」へもどる

トップページへもどる