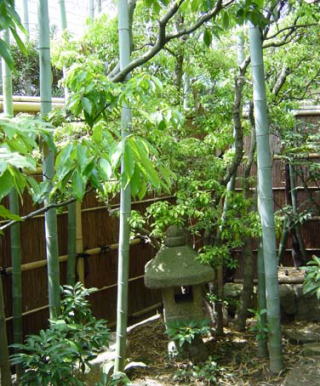トップページへもどる


2003年4月28日 「やぶ医者?竹の子医者?」
5月の連休を前にして、春の味覚である竹の子もそろそろ終わりとなるころですが、マイ・ホームタウン吉良町の山間部は竹の子の生産地でもあるために、この季節になると、たくさんのかたから堀りたてを頂戴します。竹の子ごはん、若竹煮、木の芽田楽などに調理しても食べきれないほどですが、朝堀りの新鮮な竹の子の味は絶品で、スーパーマーケットで水煮にされて売られているものとは比較になりません。
亡くなったわたしの父は茶道と陶芸を愛する趣味人であり、その趣味が高じて自宅に茶室を普請し、茶庭をいじることを生きがいとしていました。「自分はやぶ医者だから、その住まいにふさわしい竹やぶをつくるのだ」と言いながら、かなり若いころから屋敷のあちこちに様々な種類の竹を植え続けたのです。父が植えた竹たちはりっぱに成長しており、この季節になると庭のそこかしこで竹の子が顔を出すようになってしまいました。これを放置すると、竹の子たちは成長して竹になり、わが家は本当にやぶの中に埋もれてしまうので、それを引っこぬく処理が必要なのですが、地中深く根をはる竹のこと、これがなかなか大変な作業です。この季節になると、竹の子堀りをしていて腰を痛めた患者さんが来院されますが、さもありなんと思います。
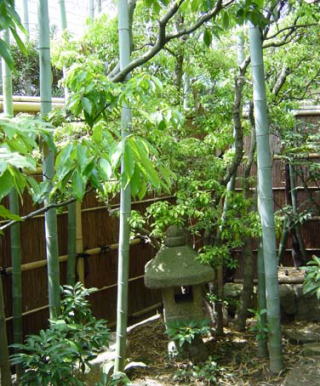



<宮崎医院の敷地のなかは竹だらけ、地中から顔を出した竹の子のあたまもあちこちに>
江戸のむかしから、腕の悪い医者は「やぶ医者」とか、単に「やぶ」などと呼ばれており、古典落語に出てくるインチキ医者は、たいてい「藪井竹庵(やぶいちくあん)」という名前です。なぜ、腕の悪い医者を「やぶ」と呼ぶようになったかについては諸説がありますが、患者の見立てが悪く、医学の事情に暗いという意味で「野暮(やぼ)な医者、やぼ医者」が、いつのまにか「やぶ医者」に変わっていたとする説が有力なようです。さらに、「やぶ医者」から派生したことばに、「竹の子医者」というのがありますが、こちらはまだやぶにもなれない、若くて未熟な医者のことをさすようです。宮崎家の庭はまさに「藪井竹庵」の一歩手前になっていますが、医者の腕前のほうだけは、野暮(やぼ)な医者=やぶ医者ではなく、粋(いき)な医者と呼ばれるようになりたいものです。
2003年4月21日 「学校医デビュー & 吹奏楽部のメモリアル」
地域に密着して仕事をする開業医は、自分の診療所で患者さんを診察する外来業務以外にも、公衆衛生に関する様々な業務をこなさなければいけません。町保健センターでの予防接種、介護保険の認定審査、産業医の契約をしている企業の労働衛生管理など、大学病院の勤務医時代には、経験したことのない仕事の依頼がつぎつぎに舞いこんできます。そのなかでも、子供たちの安全と健康を守る、学校保健の仕事は重要な位置をしめており、わたしは昨年度から離島(はなれじま)保育園の園医に、今年度から母校である吉良中学校の校医に任命されました。
学校医に任命されてからの初仕事として、4月18日に吉良中に行き、新1年生の内科検診をやってきました。わたしが在学中の30年前と変わらぬ校舎に入ると、さすがに「なつかしい」という思いでいっぱいになります。わざわざ出迎えてくださった校長の高柳先生は、わたしの中学時代の恩師のひとりなのですが、校長と校医という立場になって再会できたことも感慨深いものがあります。
わたしの吉良中での思い出は、クラブ活動である吹奏楽一色で、ともかく年がら年中ラッパ(トロンボーン)を吹いてすごしていました。すぐれた指導者に恵まれたために、吹奏楽コンクールの全国大会に中2、中3と2年連続で出場という、生涯忘れることのできない体験ができました。2年生の時の全国大会は秋田市で開催されたのですが、もちろん秋田新幹線など影も形もない頃のこと、丸一日かけて電車にゆられて吉良から秋田まで遠征したのです。その時に、大切な楽器を吉良町土木課の黄色いダンプカーに積み込んで、遠路はるばる秋田まで運んでくださったのが、若き日の高柳校長先生なのでした。
中学校に出かける前に、ネットで「吉良中学校」をキーワードに検索して遊んでいたら、何と「吉良中学校吹奏楽部&OB会ホームページ」なるものがみつかりました。知らなかった。さっそくのぞいてみると、最近の活動報告ばかりでなく、「沿革」というコーナーで過去の歴史がまとめてあったりして、なかなか充実したサイトではありませんか。これは当院HPのリンク集に加えなければと、管理人さんあてにメールしたところ、現在の吹奏楽部顧問である嶋崎先生のページであることが判明した次第です。現役部員のみなさま、伝統ある吉良中サウンドを絶やさないように、いっぱい練習してくださいね。
学校医の仕事としては、この後も2年生、3年生の検診や予防接種などの予定が続きます。母校の後輩たちが元気なからだで、勉強やクラブ活動に打ち込むことができるように、学校医1年生のわたしもがんばって活動しなければ。

<第24回全日本吹奏楽コンクール(1976年11月、横浜)に出場した時の舞台写真。
当時14才、当然のことながら、若いです!細いです!>
2003年4月10日 「N95マスクで武装せよ!」
3月29日付けの日誌をアップしてからも、謎の新型肺炎「重症急性呼吸器症候群(SARS)」の騒動は世界の各地に拡大するばかりで、香港あたりではえらいことになっていますね。幸い本日までのところ、日本では本物のSARS患者は発生していませんが、この様子では遠からず上陸してくるのは避けられないでしょう。内科専門医を対象にしたメーリングリストなどを通じて、ネット上では毎日この病気の最新情報が、大量に配信されていますので、わたしも有益な情報が得られればこのHPでご紹介していくつもりです。
香港の映像をテレビで見ると、街を歩くひとびとが様々なタイプのマスクをつけている姿が流れています。SARSの感染経路としては、患者の唾液が飛ぶことにより感染する「飛沫感染」が主体であると考えられていますので、流行地の住民はマスクによる自衛策をとるしかないのでしょう。しかし、飛沫感染だけでは説明のつかない事例もあり、最も恐ろしい「空気感染」説も完全には否定はできないようです。
しかし、感染症の専門家たちは、流行地の一般住民が通常のマスクを装着しても、SARSの感染予防に効果がないという考えを持っています。その理由は、病原体から身を守るためには、普通の医療用マスクではダメで、特殊なマスクを使用しなければならないからです。WHO(世界保健機構)やCDC(アメリカ疾病管理センター)では、SARS感染患者を隔離・収容する病院のスタッフが使用すべきマスクとして、「N95マスク」を推奨しています。このマスクは「1ミクロンの粒子を95%以上濾過する能力があり、顔面接触縁からの漏出率が10%以下」という基準をクリアしなければならず、もともとは排菌している結核患者を収容する隔離病棟で使用されているものなのです。
先日の事件(3月29日の日誌をみてください)のこともあり、宮崎医院としてもわたし自身を含めたスタッフ全員の安全のために、このN95マスクを用意しました。現在、国内でもこのマスクは非常に品薄であり、手に入りにくい状況だそうです。もちろん、こんな物騒なマスクをつけて診察しなければならない事態は避けたいと祈っておりますが・・・

これが「N95マスク」、備えあれば憂いなし?

「過去の院長日誌を読む」へもどる

トップページへもどる