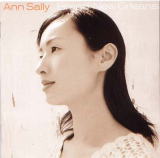�g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ�


�@�f�@���Ŋ��҂���u�搶�̓N�[���E�r�Y�A���Ȃ��́H�v�Ɛ����������܂����B�킽���́A�����l�N�^�C�����߂Ďd�������Ă��܂�����A����c���̃Z���Z�C�����ɂȂ���āA�y���ɂ��Ă݂���ǂ����Ƃ�������Ă݂����ł��B���̊��҂���ɂ́A�u�l�N�^�C�Ȃ��ŁA�V���c�����ɒ����Ȃ���قǁA����������Ȃ��ł�����v�Ƃ��������Ă����܂������A�u�ȃG�l�E���b�N�v�̓�̕��ɂȂ邾�낤�ƁA�o�J�ɂ��Ă����N�[���E�r�Y�̃L�����y�[�����A�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��������B
�@���߂ĂȂ��߂Ă݂�ƁA�u�N�[���E�r�Y�v�Ƃ������t�́A�u�N�[���v�͗������Ƃ����Ӗ����낤���A�u�r�Y�v���킩���B�L�����y�[���̊��U������Ă������Ȃ̃z�[���y�[�W���݂�ƁA"COOL BIZ"�ƂÂ�炵���B������"biz"���Ђ��Ă݂�ƁA�u�E�ƁA�������Ӗ����鑭��Abusiness�̒Z�k�`�v�Ƃ���A�p��Ƃ���"show biz"���������Ă��܂����B�ȁ[�A����ȃt�@�b�V�����ƊE�̗p�ꂾ�Ǝv���Ă�����Abiz�Ƃ����̂�business���L�U�ɏk�߂������̂��Ƃ������̂��B
�@����ɂ��Ă��A�e���r�Ŋt����c�������̃N�[���E�r�Y�E�X�^�C����q������ƁA�u���f�Ń����g�Q���B�e�̏��Ԃ�҂��Ă���Ƃ��̂�������v���A�u�S�u���Ɍ쑗�����Ƃ��̗e�^�ҁv�݂����ȃV���c�p���肪�ڂɂ��āA�z���g���������Ȃ�܂��ˁB�킪���ōł��_���f�B�Ȑa�m�ł��������F���Y�́A�V�������̗[�H���ɁA�e�[�u���ɍ���ƁA�u�l�N�^�C�������Ɏ���v�ƌ������ƁA�Ȃ̐��q�͌���Ă��܂��i�u���F���q���`�v�E�V�����j�B���F���Y�͑吳8�N��17�ŁA�p���P���u���b�W��w�N���A�[�J���b�W�ɗ��w���Ă��܂����A���̗������ɂ����āA�l�N�^�C�Ȃ��ŐH���ɗՂނ̂́A���ŐH����͂ނ̂ɓ������Ƌ�����ꂽ�����ł��B���F���Y�������Ă��āA�N�[���E�r�Y�p�̋c�������̃t�@�b�V������ڂɂ�����A�u�v�����V�v���ɔ�����v�ƌ����Č��{�����Ȃ�������B
�@����ȃV���c�p�̓��{�l�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�C�^���A�̟������̂����́A�u�Z���c�@�E�N���o�b�^�iSenza
Cravatte �j�v�ƌĂ��A�^�C�Ȃ��ŃX�[�c�ƃV���c�𒅂�t�@�b�V������҂ݏo���܂����B�u�Z���c�@�v�́u�`�Ȃ��v�A�u�N���o�b�^�v�́u�l�N�^�C�v�Ƃ����Ӗ��̃C�^���A��ł�����A���̂܂�܂Ȃ�ł����A�����̃m�[�l�N�^�C�ł͂Ȃ��āA�l�X�Ȍ��܂育�Ƃ�����悤�ł��B���Ȃ킿�A�㒅��V�]�[���������ăV���c�̘I�o�����Ȃ��^�C�v��I�ԁA�V���c�͋����J�������Ȃ��悤�ɋ݂��������̂�I�ԂȂǁA�Z���c�@�E�N���o�b�^�ɂ͒����Ȃ��̃R�c������Ƃ����킯�B�C�^���A�̈ɒB�j���������K����������ǁA�W���p�j�[�Y�ɂ͏��X�n�[�h���������ˁB�Z�{�q���Y�̎ႫIT���҂�A�e���r�̃��C�h�V���[�ɏo�Ă���R�����e�[�^�[�����ɂ́A���̃X�^�C���������̂ł����A�������悭���܂��Ă���j���́A�قƂ�ǂ��܂�����́B
�@�킽�����d������Ƃ��ɁA�K���l�N�^�C�����߂Ă���̂́A��t�Ƃ��Ă̏C�Ǝ���ɁA�����ɂ��Č������d���܂ꂽ����ł��B���C��Ƃ��ďA�E�������H�����ەa�@�ł́A1�N���A2�N���̌��C��́A�����̃P�[�V�[�i�x���E�P�[�V�[�����Ă����悤�ȁA�ێ�̒Z�����߂̂��Ɓj�ɁA���̒��Y�{���̐����𒅂邱�Ƃ��`���Â����Ă��܂����B3�N�ڂɂȂ�ƁA����ƒ������߂̒��p���������̂ł����A�l�N�^�C�Ȃ��̂��炵�Ȃ��X�^�C���́A��ɔF�߂��܂���B���̌�ɋΖ��������c�ی��q����w�a�@���t�E���w�Ö@�Ȃł��A���H���Ɠ����悤�ɁA������Ƃ����g�����Ȃ݂Őf�Â���Ƃ�����ǂ̋C�����������̂ŁA�l�N�^�C�Ȃ��Ŏd�����邱�Ƃ͂���܂���ł����B��҂̕����́A�����l���H����ȂƓ����ŁA�ǂ��ŏC�s�������A�ǂ�Ȑ�y�����Ĉ�������A�Ƃ����Ƃ���Ō��܂���̂ł��B�������A�������ꂽ���������̔��߂𒅂���҂ɏo�������A���̐搶�͂��܂�ꗬ�̂Ƃ���ł͏C�s���Ă��Ȃ��������̂Ǝv���ĊԈႢ����܂���B
�@�uneat�ł��邱�Ƃ���{�B�����ł������ς肵��������S������B�j���̏ꍇ�̓T�C�Y�̂��������C�V���c��g�ɂ��āA�l�N�^�C�����ԁB�l�N�^�C�̌��іڂ𐮂��邱�Ƃ��Y��Ă͂����Ȃ��B�������ɂ����ӂ���B�T���_���͗����Ȃ��B�����̏ꍇ�A�A�N�Z�T���[�͍ŏ����Ƃ��A���ς��T���߂ɂ���B�v�i�u���ȊO���f�Ã}�j���A����3���v�E��w���@�@p2�����p�j
�@��̕��͂́A���H������Ɏw����Ƃ��Ă킽�����������b���Ă����������A�g�����l�搶�i���E�k�C����w��w�������ȏ������j�������ꂽ�O���f�Ã}�j���A���̖`���ŁA�u��t�̃}�i�[�E�����v�ɂ��Č��y����Ă��镔���������������̂ł��B"neat"�Ƃ́A�u�������ς肵���v�Ƃ��A�u�g�����Ȃ݂̂悢�v�Ƃ����Ӗ��̉p��ł����A���҂����O�ɂ����Ƃ��ɁA�ǂ�ȕ���������Ηǂ������A���ɖ����ɏq�ׂ��Ă���ł���B�킽���͋삯�����̂��납��A���̂悤�ȋ�����Ă����̂ŁA������N�[���E�r�Y���ƌ����Ă��A�����ȒP�ɂ̓l�N�^�C���O���Ďd�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B���F���Y�ɂȂ���Č����A����͂킽���́u�v�����V�v���i�����E�����j�v�ɔ�����s�ׂł�����B
 �@�@�@
�@�@�@
�����̐f�@�X�^�C���i���j�ƁA�N�[���E�r�Y�H�i�E�j��V�]�[�����r���Ă݂�
��
�N�[���E�r�Y�Ƃ��������āA�P�Ƀ^�C���͂����Ă݂�����������
��
�Ȃ��\���Z�ʼn��w�����Ă�搶�݂����Ȋi�D�ɁE�E�E
�Z���c�@�E�N���o�b�^�͂ނ�������
��
�^�C�g���́u�T���V���O�E�N�[���v��
�W���[���E�N���X�e�B��COOL�ȃ��R�[�h�ւ̃I�}�[�W��
�@6��8���̖�A���m���ΘJ��قōs��ꂽ�A�����X�J�p���_�C�X�I�[�P�X�g���i�����ăX�J�p���j�̃��C�u�ցB
�@�I�[�v�j���O��1�Ȗڂ���q�͑������B�X�^���f�B���O�̃R���T�[�g�Ȃ�āA���N�Ԃ肩����B�o���h���q���ŏ�����p���[�S�J�ŁA��ђ��˂Ă���܂���B�L���z�[���̋q�Ȃ��A���C�u�n�E�X�̃t���A�݂����ɂȂ����Ⴂ�܂����B���ꂶ��A�݂�Ȃŗx��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��ł���B
�@�X�J�p���́u�X�J�v�ƌĂ��W�������̉��y�𒆐S�ɉ��t����o���h�ŁA�z�[���Z�N�V�����i�g�����y�b�g�A�g�����{�[���A3�{�̃T�b�N�X�j�ƃ��Y���Z�N�V���������킹�đ���10���̒j�����ŕҐ�����Ă���܂��B�X�J�p���Ȃ�Ēm��Ȃ���Ƃ����ЂƂ����ł��A�L�����ʃ`���[�n�C�u�X���ʏ`�v��CM���y�ȂǂŁA�����Ɣނ�̋Ȃ����x�����ɂ��Ă���͂��B����15���N���ނ����Ă���ɔ��͂␦�����������݂����ŁA�����o�[�S�����X�e�[�W�����ς��ɖ\��܂���Ẵp�t�H�[�}���X�A�z���g���|����܂����B
�@�X�J�p�����܂��C���f�B�[�Y�Ƃ��Ċ������Ă��������ɁA�����q��iKYON KYON�A��������40�����Ă˪�E�E�E�j�̖��ՁuBallad Classics 2�v�i1989�N�j�̂Ȃ��ŁA�ޏ��̉̂̃o�b�N�ʼn��t���Ă����ނ�Ə��߂đ����B�u�ȁA�Ȃ��̃o���h�́H�I�v�Ƃт����肵�āA���ꂩ��M�S�ȃt�@���ƂȂ�܂����B�����܂ł��ƒ����ɔނ��CD��f����i��ǂ������Ă��܂������A���C�u�̉��t�ƂȂ�ƁA���W���[�E�f�r���[�����1990�N��������r�̃{�g�����C���i���ꂪ���É������Q���H�j�Œ����Ĉȗ��ł��B�Y�܂ꂽ�Ƃ�����X�J�p���̉��y���q��̂����ɂ��Ĉ�������q���A�ŋ߂ɂȂ��ăg�����y�b�g�̗��K���n�߂����Ƃ������āA�u���ЃX�J�p���̃��C�u���ς����̂ł����v�ƃ��N�G�X�g���Ă������̂ł�����A�d�q�`�P�b�g�҂���TICKET���Q�b�g���A����͕��q�ӂ���̃R���r��g�݁A�E��ʼn��ɏ�肱�킯�Ȃ́B
�@�u�X�J�@Ska�v�Ƃ́A���Q�G�ɐ悪���āA1950�N��㔼����W���}�C�J�Œa��������O���y�i�|�s�����[�E�~���[�W�b�N�j�̂��ƁB�X�J�̓����͒��ˏオ��悤�ȃ��Y���ɂ���A���C���̔��q�Ɣ��q�̊ԂɁA�Ɠ��ȃA�N�Z���g�����Ă��܂��B���̂�����u���ł��v�̃X�^�C���������ŁA���̃��Y�����u�X�L���b�A�X�L���b�v�ƕ������邱�Ƃ���A�X�J�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ̐�������݂����B���̌�A�X�J�̓W���}�C�J�����łȂ��A�����h�����͂��߂Ƃ��āA���E�e�n�ɍL�����Ă����܂����B�X�J�p���͎��������̉��y���u�g�[�L���[�E�X�J�v�ƌĂ�ł��܂����A���{�ł��̎�̉��y���L�߂��ő�̌��ю҂Ƃ����Ă��悢�ł��傤�B
�@�X�e�[�W�̓j���[�A���o���uAnswer�v����̃i���o�[�𒆐S�ɂ��āA�n�C�e���V�������ێ������܂�܂ŁA2���Ԃ݂�����x�݂Ȃ��B���q�͂Ȃ������Ⴂ����2�`3���̃O���[�v�������̂ł����A���Ȃ�}�j�A�b�N�Ȉ��D�Ƃ̕��͋C��Y�킹�Ă���̂��A�A�C�h���n��b�N�n�̃R���T�[�g�Ƃ̂������ł��傤���B�X�J�p���̃��C�u�ɏW�܂郄���O�����́A�݂Ȃ����ς��s�V�悭�n�W���Ă�������Ⴂ�܂����̂ŁA�ƂȂ�ŗx���Ă�����C�ȃI�W����Ƃ��̑��q��1�����A���S���ĐS�n�̂悢�O���[���ɐg���܂����邱�Ƃ��ł��܂����B�����X�J�̃r�[�g�ɂ̂��ėx��Ȃ���v�������ƁB����͂��Ȃ�̉^���ɂȂ�A�����I�ɐS�������オ��̂ŁA����ςȗL�_�f�^���ɂȂ��āA�]���Ȏ��b���R�Ă��邼�B���Ԃ����X�e�[�W�Ɍ������ē˂��グ��ƁA���X�̐f�Âł̃X�g���X�������Ă䂫�A�����^���w���X�ɂ��ǂ��e��������݂����B���ꂩ��́A�u���C�u�Ō��N�Â���v���i���I���W�������R�����g�ˁj�B���p�����������ƂɁA�������߂��ʉ�����ɂ����Ƃ���A�������ӂ���ĕ����ŃR�P�����ɂȂ�A�����̔N��Ɏv�����͂��邱�ƂɂȂ����@���ł����B�ł��A�y���������B�܂��s���ėx�邼�I

�{���@�̃K�[�f���ł́A
�������܁u���������v���Ԑ���
��
���������̉Ԍ��t�́A
�u�ڂ�C�v�Ȃ��āE�E�E
�@�����E���W�̌���ł́A�u�V�l�{�P�v��u�s���v�ɂƂ��ĕς���āA�u�F�m�ǁv�Ȃ�V���ȕa������������ƒ蒅���Ă��܂����l�q�ł��ˁB�F�m�ǂɂ�����ƁA�]�̂Ȃ��ɂ��镪�����u�L���̓��L���v�̃y�[�W���A�Ƃ���ǂ��딲�������Ă����A����������̈Ӑ}�Ƃ͖��W�ɁA����C�܂܂Ƀ|���|���Ɣ��������Ă����Ă��܂��B����ȁA�F�m�ǂ̊��҂�������˘f���⋰�|���A�����̂������ŁA���Ȃ��`���o�����{�����Љ�܂��傤�B�S���̏��X�œ����X���������A�u�����̓X�Ŕ��肽���v�Ǝv�����{�𓊕[���đI�ԁu�{������v���������ł����B2005�N�́u�{����܁v��2�ʁi����18��R�{���ܘY��܁j�ɋP�����A�����_���́u�����̋L���v�����̖{�ł��B�{��������ǂ���z�M����Ă���A���X�̓X������u���萻�v�̏Љ�����p����ƁE�E�E
�@�����}�ȍK����ˑR�D�����Ռ��̍��m�u��N���A���c�n�C�}�[�v�B�������Ɏ����Ă䂭�L���Ɛl�i�B�Ƒ��A�d���A�S�Ă̊�����������Ői�s����Ǐ�E�E�E�@���s�s�Ȕ��ǂɕ�����o���Ȃ�����A������O�̓���ƌ��������̂Ȃ����̑f���炵���ɉ��߂ċC�Â����Ă�������B
�@�������͂킪�g��������Ȃ��h�Y��䂭����h�B�L���}���Ƃ��Ė����d���ɒǂ��Ă��鍲���͕��Y�ꂪ�����Ȃ��Ă��鎩���ɕs���������a�@�����ɍs���B�f�f�͎�N���A���c�n�C�}�[�B�d��������A�Ȃ�����A�����Ď����͊Ԃ��Ȃ��c���ɂȂ�B�܂����v���Ƃ��������Ƃ͔��ɗ�ꗎ����L���B�u����Ȃ��v�a�C�ƁA�ǂ����������Ă����̂��A���̍�i�̌����͔������B�Ⴆ�����A������������A�ǂ������邾�낤�A�l�������������B
�@�u�����̋L���v��50�ɂȂ郄����̍L���㗝�X�c�ƕ������A�u��N���A���c�n�C�}�[�v�ɂ��F�m�ǂƐf�f����Ă���̏o�������A��l�̂ŏ����Â�����L�̂������ō\������Ă���t�B�N�V�����ł��B�ŏ��͂����́u���̖Y��v�Ǝv���Ă����ǏA�������ɐ[���ɂȂ��Ă䂫�A�d����ƒ�Ŏx����������l�q���A���҂���{�l�̎��_�Ń��A���Ɍ���Ă���̂��V�N�ł���Ǝv���܂����B�a�i�s���������̌㔼�ɂȂ�ƁA������Y��ĂЂ炪�Ȃ��肪�ڗ����͂ɕς���Ă��܂��B���̎�@�̓_�j�G���E�L�[�X�̃J���gSF�u�A���W���[�m���ɉԑ����v�ł����ʓI�Ɏg���Ă��܂������A���̏����ɂ����Ă��ǂޑ��͐g�ɂ܂����v�������������܂��B
�@�u�����̋L���v�Ƒ��O�サ�āA�u�F�m�ǂɂȂ�ƂȂ��w�s���ȍs���x���Ƃ�̂��v�i�����L�i�E���A�͏o���[�V�ЁE���j�Ƃ����{���ǂ݂܂����B������͏����ł͂Ȃ��A�Տ��S���m�Ƃ��āA�����̔F�m�NJ��҂���̃P�A�ɂ�����������҂��A���҂���́u�S���v�ɏœ_�ĂāA����Ȑl���u�s���v�Ɗ�����l�X�ȍs�����A�Ȃ��N����A�����Ӗ�����̂����A��ʂ̓ǎ҂�ΏۂƂ��Ă킩��₷��������������[�����e�ƂȂ��Ă���܂��B���Ƃ��ΔF�m�ǂ̂��N��肪���̖Y��͌������̂ɁA�I�݂ȁu����b�v������̂͂Ȃ����H�{���ŗᎦ����Ă���P�[�X�ł́A�䏊�̌˒I�ɉB���Ă������݂��Ȃ��Ȃ��Ă���̂ŁA���ł��F�m�ǂʼnߐH�C���̂����������ɁA�u��������A�����ɂ������݂���m��܂��v�Ɛq�˂�ƁA�����������͑S�������ŐH�ׂĂ��܂����̂ɁA�u�݂���H�����A���ׂ̑����������Ă��Ă���ĂȂ��B���̎q�ɂ�������v�Ɠ�����B���āA�ǂ����Ă���Ȍ��ۂ�������̂��A���҂ɂ������ǂ�ł݂܂��傤�B
�@���������́A����Ȃ�������A��f�ГI�ɂ����Ȃ��ƁA�u���Ԃ��ł͂Ȃ����v�u�����Ƃ������낤�v�Ƃ�����ɁA�z���łȂ����������肷�邱�Ƃ�����܂��B�F�m�ǂ̕����A�f�ГI�ɂ����Ȃ������Ȃ����킹�邽�߂ɁA�z���ŕ₤���Ƃ͂���̂ł����A�L���̌����߂��Ƃ��������ʁA�u���Ԃ����낤�v�ł͂Ȃ��A�u�����Ȃ̂��v�Ɗm�M���Ă��܂��悤�ł��B����͑z���ł���Ƃ����F�����Ȃ����肩�A�b�������Ă���Ƃ������o���Ȃ��A���{�l�ɂƂ��Ắu�^���v�ɂȂ��Ă��܂��킯�ł��B���̂悤�Ȃ���b�͐^������ттĂ��āA������m��Ȃ��l�������Ɩ{���̂��ƂƊ����Ă��܂����Ƃ������A�܂��A�����Ă��͂��{�l�ɂƂ��ėL���ȓ��e�̂���b�ɂȂ��Ă��܂��B���̃P�[�X�ł����ƁA�u�݂��Ȃ��Ɖł������B�N�����H�ׂ��ɈႢ�Ȃ��v�Ǝv�����Ƃ͂����Ă��A�u�������S���H�ׂ���������Ȃ��v�Ƃ��������ɂ͋C�����͌������Ă����Ȃ��̂ł��B��
�@�{���͂��̂悤�ȁu�s���ȍs���v��20�̎���ɂ܂Ƃ߂��Ă���A���ꂼ��ڍׂɕ��͂���Ă��܂��B�킽��������̐f�Â̂Ȃ��ŁA��������^��Ɋ����Ă����A�F�m�ǂ̊��҂���̕s���ȍs���E�����̓䂪�����āA�ڂ���E���R���{���{���Ɨ����܂����B�u���N��肪���C�Ȏq�ǂ��ɕԂ�v�ȂǂƂ�����������C���[�W������āA�u�傫�ȗc���v�ɐڂ���悤�ȑԓx�ŁA�F�m�ǂ̃P�A�����邱�Ƃ��A�ǂ�ȂɊ��҂���̂�����������邱�ƂɂȂ�̂����A�킽���ɂ��悤�₭�킩���Ă����̂ł��B���̖{�Ɓu�����̋L���v�s���ēǂނƁA�����̍�҂͔F�m�ǂ̊��҂���̐S���ɂ��āA��ς悭������Ă����i�̎��M�Ɏ��g�܂ꂽ���Ƃ��ǂ��킩��܂��B�F�m�ǂ̖����ɂȂ�ƁA���N�ꂻ���������̔z��҂̂��Ƃ������A�N�ł��邩�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����A�u���t�◝�����āA���S�ł��鑊�肾�Ƃ������Ƃ͂킩��v�����ł��B���̂�����̐S�����d�v�ȃ��`�[�t�ɂ��āA�u�����̋L���v�̃��X�g�E�V�[���͈�ۓI�ɕ`����Ă��܂��̂ŁA���Ђ���ǂ��������B
�@���������Ɂu�����͂킪�g�v�̔F�m�ǂł����A�����ɂƂ��Ă��������̂Ȃ��������L���i�������[�j�������_���ɏ����Ă䂭�̂́A���ɔ߂������Ƃł͂���܂��B
�@"In my heart you will remain: My stardust melody, the memory of love's refrain"
�@�i���̐����̃����f�B���A���̒��ׂ̎v���o���A�ڂ��̐S�̒��ɂ��܂ł������܂��Ă���j
�@����͗��̎v���o���i�ق������j�ɑ������A���ȁu�X�^�[�_�X�g�v�̍Ō�̃t���[�Y�B�u�����̃����f�B�v��u���̒��ׂ̎v���o�v�Ȃ́A�ł���Ŋ��܂ŏ����Ăق����Ȃ��L���̕M���Ȃ��ǁA�킽�����F�m�ǂɂȂ����������ɂ́A����ȃL���C�Ȏv���o�͂����ɏ��ł����܂��āA���܂ł������Ȃ����w�̃e�X�g��A�S�ׂ��������C��̂���̓����̋L���Ȃ�Ă��̂��肪�A�u�ڂ��̐S�̒��ɂ������t���C�����Ă���v�悤�Ȏ��ԂɂȂ肻���ł��ȁB
�@
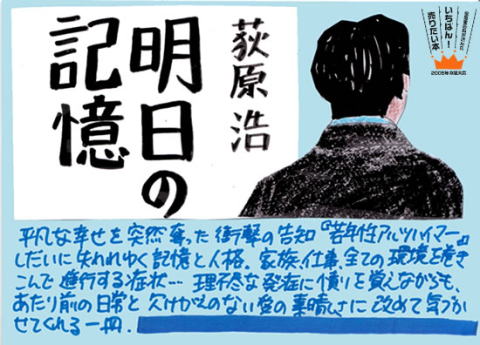
POP�������삵���u�����̋L���v��POP
��
�uPOP�i�|�b�v�j�v�Ƃ́E�E�E
�{������̕��ςݑ�ɂ҂傱��Ɣ�яo�Ă���D�̂���
�ȒP�Ȑ�`����Ɩ{�̏�L�ڂ���Ă��܂�
�@�u�g�̕\������Q�v�Ƃ����a�C���������ł����B�ȂɑS�R�m��Ȃ��H�@���������A�����S���������B��҂ł���킽���ł����A�����̊Ԃ܂ŕ��������Ƃ��Ȃ������a���Ȃ̂ł�����B�������A���̕a�C�͊�a�ł����ł�����܂���B�݂Ȃ���̂܂��ɂ��A���҂���͂�������͂��B�����{���@�̊O���ɂ����āA���̕a�C�̊��҂����͖����̂悤�ɗ��@����Ă���̂ł��B
�@�킽�����u�g�̕\������Q somatoform disorder�v�Ƃ����a���ɂ͂��߂ďo������̂́A�܂��J�Ƃ��ĊԂ��Ȃ��A���悻2�N�O�̂��ƁB�������_�̂悤�ɂ��邢�A�����Ƃӂ���A�������ƂȂ��d���A�݂̂����肪���J���J����Ƃ������A���ʂȏǏ��i���銳�҂����@����܂����B�������A�l�X�Ȑf�@�⌟�����s���Ă��A�����̏Ǐ�������������悤�ȑ���ُ̈�������邱�Ƃ��ł��܂���B�����ŁA���a�ɂ��g�̏Ǐ���^���čR���܂��������Ă��A���������ɏǏ�̉��P������܂���B�قƂقƍ���ʂĂāA���Ƃ����҂����������āA�߂��̕a�@�̐��_�ȊO������f���Ă��炢�܂����B���̂Ƃ��̏Љ��̕Ԏ��ɋL����Ă����a�����u�g�̕\������Q�v�������̂ł��B
�@�킽�����w������Ɏ�u�������_�Ȃ̍u�`�ł́A����ȕa�C�̂��Ƃ͋����܂���ł����B�������A�ŐV�̐��_��w�̃e�L�X�g�u�b�N���J���Ă݂�ƁA�m���ɐg�̕\������Q�Ƃ������ڂ��ڂ��Ă���ł͂���܂��B���ȏ��̋L�ڂ�ǂ�ł݂�ƁA1980�N�ɃA�����J���_��w����s�������_��Q�̕��ނƐf�f�̎�����iDSM-�V�j�ŁA�V�����g�p�����悤�ɂȂ����p��ł��邱�Ƃ��킩��܂����B���̍ŐV�łł���DSM-�W�ł́A�g�̕\������Q�̂Ȃ��Ɋ܂܂��a�C�Ƃ��āA�u�g�̉���Q�v�A�u�]������Q�v�A�u�u�ɐ���Q�v�A�u�S�C�ǁv�Ȃǂ����X�g�A�b�v����Ă��܂��B�������A���_�Ȃ̈�҂łȂ����̂ɂƂ��ẮA�Ȃ��݂̂Ȃ����p�ꂪ�Ȃ���ȏ��̋L�q���A���m�ɗ�������͍̂���ł����B���̓����̂킽���̗����̂������́A�u��ʓI�Ȑg�̈�w�ł͑S�������̂��Ȃ����炾�̏ǏA�����Ԃɂ킽���łɑ��݂��邪�A���̏Ǐ�̌��������a��s����Q�Ƃ��������̐��_�����ɂ����̂ł͂Ȃ��ꍇ���A�g�̕\������Q�ƌĂԂ̂��ȁv�Ƃ������炢�̂��̂ł����B���̂悤�ɗ������Ă��A���̕a�C�̃C���[�W�ɂ��ẮA���ƂȂ��ߑR�Ƃ��Ȃ��������c�����̂ŁA�g�̕\������Q�͏�ɋC�ɂȂ鑶�݂Ƃ��āA�킽���̓��̈�p�����̌���苒���Â����̂ł��B
�@�J�ƈ�ɂȂ��āA������ʐH��������Ƃ́A�����قǂ̊��҂���̂悤�ɁA��w�I�ɂ͐���������Ȑg�̂̏Ǐ��i���銳�҂��A�����ς����@�����Ƃ������Ƃł����B�킽�����܂߂����{�̗Տ��ソ���́A���̃^�C�v�̊��҂���ɏo��ƁA�u�s��D�i�nj�Q�v�A�u�����_�o�����ǁv�A���w�l�ł���u�X�N����Q�v�Ƃ������a�������Ղɕt���Ă��܂����B�a���͕t���Ă��A���̏Ǐ�͂����Ƃ��ǂ��Ȃ�Ȃ����A�f�@���Ԃ����͔��ɒ����Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�ǂ��炩�Ƃ����A�f�Â��h�����Ă������j������܂��B����A���Ăł͂��̂悤�Ȍ��ۂ��u�g�̉��@somatization�v�ƌĂ�ł�����Ɍ�������Ă���A�u���҂���̔w�i�ɉB��Ă���S���I�A�Љ�I��肪�A���炾�̏Ǐ�ɒu��������ꂽ���́v�ƍl�����Ă��܂��B�A�����J��[���b�p�ɂ́A�u�����_�o�����ǁv�Ȃ�ĕa���͂Ȃ��̂ł��B�g�̉���������a�C�Ƃ��ẮA������S�g�ǂ��͂��߂Ƃ��āA���a�A�s����Q�A�K����Q�A�����Č��̐g�̕\������Q�Ȃǂ��m���Ă���킯�ł��B���̂����ŁA���a�ɂ͍R���܂��A�s����Q�ɂ͍R�s���܂��A���ɂ悭�����̂ŁA�K�Ɏ��Â��s���Ί��҂���̑i���邩�炾�̏Ǐ�͂��ꂢ�ɏ����Ă䂫�܂��B�������A��������̊��҂��������Â��Ă��������ɁA�R���܂�R�s���܂��̂�ł��A�قƂ�ǏǏǂ��Ȃ�Ȃ����҂��������݂��邱�ƂɋC�����܂����B�����炭�A���̃O���[�v�̊��҂��������A�u�g�̕\������Q�v�̔��e�ɑ�����P�[�X���낤�Ƃ������Ƃ��A�o�����d�˂Ă��������ɁA�킽���ɂ�����Ƃ킩���Ă����̂ł��B
�@�ŋ߂ɂȂ��ċ��R�̋@���A���̕a�C�ɂ��Ă̂��킵�������������Ă������̖{�����܂����B�ӊO�Ȃ��ƂɁA���̖{�͈�w�̐�发�ł͂Ȃ��A��ʂ̓ǎ҂�Ώۂɂ����V���ŁiPHP�V���j�ł��B�{�̃^�C�g���́��̂ɂ������S�̕a�C�F�@�u�����s���̐g�̏Ǐ�v�Ƃ̕t�����������B���҂͂킽���Ɠ������m���������_�Ȃ̃N���j�b�N���J�Ƃ��Ă���������镔���i�����ׁE�������j�搶�ł��B�镔�搶�͑哯�a�@�i���É��s���j���_�ȂɋΖ�����Ă����Ƃ��ɁA��������Ȑg�̏Ǐ�ŋꂵ��ł��邽������̊��҂����f�Â��ꂽ���o�������ƂɁA�u���������a�@���_�Ȃɂ�����g�̕\������Q�̌����v�Ƃ����_�������M����܂����B���̘_�������{�����a�@���_��w��ɂ��A����11�N�x�ŗD�G�_���Ƃ��đI�o����āA�u���q�܁v�Ƃ����܂���ꂽ�̂ł��B���̘_�������Ƃɂ��āA�g�̕\������Q�Ƃ����a�C�̂��Ƃ��A��ʂ̓ǎ҂ɂ��킩��悤�ȁA�₳�������t�ŏ����Ȃ����ꂽ���̂��A�V���ł́��̂ɂ������S�̕a�C���Ȃ̂ł��B�g�̕\������Q�Ƃ����a�C���A�܂邲�ƈ�����̎��ʂ��g���āA�^���ʂ���Ƃ肠�����Ƃ����Ӗ��ł́A���{�ŏ��߂Ă̖{�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@��ʂ̓ǎ҂ނ��̖{�Ƃ͂����Ă��S���蔲���͂Ȃ��A�u��������Ȑg�̏Ǐ�v��i���銳�҂���ɑ��āA�e�Ȃ̈�҂�����ɕt���Ă����A�l�X�ȕa���̗��j�I�ȕϑJ����͂��܂��āA�u�g�̕\������Q�v�Ƃ����T�O�̗L�p���Ɩ��_�Ɏ���܂ŁA���ɏڍׂɘ_�����Ă���܂��B�킽���͂��̖{��ǂ�ł���A�{���ɐϔN�ɂ킽��ցi�����j���[����܂����B�킽�����A�{���@�Ŗ����f�@���Ă���A�R���܂�R�s���܂����܂�����Ȃ��A�u��������Ȑg�̏Ǐ�v��i���銳�҂����́A�u�ӕʕs�\�^�g�̕\������Q�v�Ƃ����f�f�ŗǂ��̂��Ƃ����m�M�����Ă�悤�ɂ��Ȃ�܂����B���̖{�̂Ȃ��̋L�q�ŁA������������̂́A�����{�̐��_�Ȃł́A�u�g�̕\������Q�v�Ƃ����a���͌��݁A�قƂ�Ǘp�����邱�Ƃ�����܂���BDSM-�W�̐f�f��͕p�ɂɗp������ɂ�������炸�A���̑區�ڂł���u�g�̕\������Q�v�͂قƂ�ǎg�p����Ȃ��̂ł��B���Ƃ����Ƃ���ł����B�Ȃ�قǁA���Ȃ̈�҂ł���킽�����A�˂���n�`�}�L�Ŋ������炵�āA���{�̐��_��w�̋��ȏ���ǂ�ł݂Ă��A���܂ЂƂs���Ƃ��Ȃ������̂́A�����������R������������ȂB�������g�������Ƃ̂Ȃ�����̎g�p�@���A���l�ɏ��ɐ������邱�ƂȂ�āA�ƂĂ��ł��܂���ˁB
�@���̐V����ǂݏI�����ォ��A����ɂ��킵�����������Ȃ�A�镔�搶�Ƀ��[���ŃR���^�N�g���Ƃ��āA���q�܂̘_�����̂��̂�ǂ݂����̂ł����A�ǂ��œ��肵����ǂ��̂ł��傤���Ƃ��q�˂����Ƃ���A�����ɘ_���̕ʍ����X������Ă��܂����B�܂������ʎ����Ȃ��c�ɂ̊J�ƈォ��́A�����܂����₢���킹���[���ɑ��āA�v���ɑΉ����Ă��������{���Ɋ����ł��B����ƑO�サ�đ����Ă����u���{��t��G���v�T�����̕\�����݂āA�܂��т�����B�Ȃ�Ɓu�g�̕\������Q�v�̓��W���g�܂�Ă���ł͂���܂��B���̎G���́A���{��t��̋@�֎��ł���A�ǎ҂͈�ʂ̊J�ƈソ���ł��B�镔�搶���͂��߂Ƃ���A���҂̌[�֊����ɂ��A���̕a�C�ɂ����悢��X�|�b�g���C�g���������Ă����̂ł��傤���B���R�Ƃ͎v���Ȃ��A�V���N���j�V�e�B�[�ɋ����A���̓��W��������ǂ��܂����B
�@�g�̕\������Q�̊��҂���́A�ŏ����琸�_�Ȃ̃N���j�b�N��K��邱�Ƃ͂���܂���B�܂��A�킽�������̂悤�ȓ��Ȃ̐f�Ï�����f����邱�Ƃ������Ǝv���܂��B���������āA���Ȃ̊J�ƈ�Ȃ�A���̕a�C���悭�������āA���҂�������Ƀ}�l�[�W�����g����͂��K�v�ł��傤�B���a��s����Q�Ƃ������āA�������ɂ����a�C�ł�����A���N�ɂ킽���Ď厡��Ɗ��҂���̊ԂɁu�ǂ����Ó����v�Ƃ����ׂ��W������ł䂭���Ƃ���Ȃ悤�ł��B����ɂ́A�����I�ɂ��S���I�ɂ��g�߂ȊJ�ƈ�̊O����������ł���ˁB����ɂ����a�C�ƕ����ƁA�₽��͂肫��^�C�v�̈�҂ł���킽���ɂƂ��āA�u�g�̕\������Q�v���߂���`���́A������Ƃ͂��܂�������ł��B
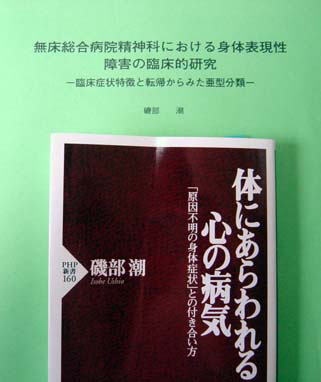
�����Ă����������u���q�܁v�_���̕ʍ��ƁA
�J�ƈ�K�� �u�̂ɂ������S�̕a�C�v�iPHP�V���j
��
�镔�搶�A���肪�Ƃ��������܂����I
��
�搶�̂��̑��̂�����
�u�l�i��Q��Q����Ȃ��v�i�����АV���j
�u���B��Q��������Ȃ��v�i�����АV���j
�ǂ�����A�������߂ł���
�@�݂Ȃ��܁A�S�[���f���E�B�[�N�̂��x�݂͂����������߂����ł����ł��傤���B�킽���͎���ŘA�x�p�ɒ��߂���ł������{�A�G���ACD�ADVD��ɂ��ėV��ł���܂����B�B��̍s�y�́A�܂������̋ߏ�ł��閼�É��s���B�ȑO����C�ɂȂ��Ă����u�����݂̂���t�فi���E����z�@�j�v�̌��w�ɏo�����܂����B���̌����͓��{�̏��D��P���ł���u�}�_����z�i����������j�v���Ɛ���z�ƁA����@�g�̖��{�q�Łu�d�͉��v�Ə̂��ꂽ����A�吳���珺�a�̂͂��߂ɂ����Ė��É��ŕ�炵�Ă����@��ł��B�ނ������c�������u�t�̔g���v�Ƃ�����̓h���}����f�����̂����L���ł��傤���B����c�q����z���A���ԓm�v������������Ă���܂����B���̌����A���Ƃ��Ƃ͓��擌��t���i���E���ǎO���ځj�Ɍ����Ă����̂Łu��t��a�v�ƌĂ�Ă��܂������A�������É��s���u�����݂̂��v�̋��_�{�݂ɂ��邽�߁A�����ؒ��̌��ݒn�Ɉڒz�E�����������̂ŁA�u�����݂̂���t�فv�Ƃ��č��N��2���ɂ߂ł����I�[�v���ƂȂ�܂����B
�@�h�i�������j�łЂ�����^�N�V�[���ɉ؊X�̌����𗣂�āA���É���ɂقNj߂��Â��Ȃ����~�X�̂Ȃ��������ނƁA���ꂢ�ȃI�����W�F�̊����������R�Ǝp������킵�܂����B��������t�قł��B���ւł����ʂ��ŃX���b�p�ɂ͂������A���ꗿ200�~����Č����̒��ւƐi�݂܂��B�����̉e�����A�A�x���̂��߂��A�v����������������̌��w�҂����܂����B��t�ق͑吳9�N����Ɍ��݂��ꂽ���̂ł����A�X�e���h�O���X���͂܂�����L�Ԃ�L����m�ٕ����ƁA�`���I�Șa�������݂���A�a�m�ܒ��̊Ԏ��ɂȂ��Ă��܂��B�v�E�{�H�ɂ��������̂́A���{�ōŏ��̗m���Z�����ЂƂ��Č��z�j�ɖ������u���߂肩���v�ł���A�X�e���h�O���X���f�U�C�������̂́A�킪���ɂ�����O���t�B�b�N�f�U�C���̑n�n�҂ł������Y���B���[��A���z�T���Ƃ��Ă͂��܂�܂���ˁB
�@�������Ɂu�d�͉��v�ƌĂꂽ�ЂƂ̏Z�܂��炵���A�����Ƃ��Ă͉���I�ȃI�[���d���ɂȂ��Ă���A�d�C�ł킩�������C��A�g�p�l���ĂԂ��߂̓d�C�u�U�[�Ȃ�Ă��̂܂Ŋe�����ɂ��Ă���܂��B�ٓ��ł͒�z�Ⓧ��Ɋւ���W���������邾���łȂ��A���y�䂩��̕��l�������Љ��R�[�i�[������A���É��̋ߑ㕶�w�قƂ��Ă̋@�\�����˂��Ȃ����{�݂ł��B�}�_����z����㉹��Y����̖��҂Ƃ��āA�p���Ō����������ɂ܂Ƃ����Ƃ����������W������Ă���܂������A�����̊��o�ł̓n�f�Ƃ��������u�P�o���v�ƕ]�������F�ƕ��ł��āA�J�^�J�i�ŕ\�L�����u�L���m�v�Ƃ��������̃R�X�`���[���ł���܂����B�u���̎p�ɎႫ���̃s�J�\���������ꂽ�v�Ȃ�Đ������Ă���܂������A�z���g������E�E�E
�@��t�ق������Ă��锒�ǃG���A�́A���É���̓����ɂ�����A�]�ˎ���ɂ͔����˂̒��E�������m�̉��~���A�Ȃ��Ă����y�n�ŁA�������珺�a�̂͂��߂ɂȂ�ƁA�ߑ�Y�Ƃ̋N�ƉƂ��������~�����܂���悤�ɂȂ�܂����B��t�ق̌��w���I���āA�u�����݂̂��v�̃K�C�h�}�b�v�𗊂�ɁA���ӂ̎�Œ���������U�����Ă݂܂������A�]�ˎ��ォ�珺�a�Ɏ���l�X�ȔN��Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ��ڂ������z�����_�݂��Ă��܂����B�{���̈Ӗ��ł�celebrity�i�Z���u���e�B�j���Z��ł����X��������ł��ˁB�������A���̃G���A������̗���ƍ��z�ȑ����łɂ͏��ĂȂ��悤�ŁA���z�T��̍D��S���h������@��͎��X�ƂԂ���āA�����ȃf�U�C���̍����}���V�����ւƎp��ς�����A�Z���u�ɓ����V�����x�T�w�̗�����������ł���l�q�B����ȐV�����Z���������A���������G���A�ɐ�������u�V���K�l�[�[�v�ɂȂ���āA���É��ł́u�V���J�x�[�[�v�ƌĂԂ��āB���߂āu�V���J�x�[�[�v�Ƃ������t�����ɂ����Ƃ��A��������ςł܂�����ɓh�肩���߂��ЂƁi�K���O���̔��ˁj�A���Ƃ�������̎q����̂悤�ȏ����̂��Ƃ��Ǝv���܂�����B���É��s���ɂ́u�V���J�x�[�[�v�̂ق��ɁA�u���S�g�W�F���k�v�Ƃ���������������炵�����炲���ӂ��������B����̎U���̓r���ŁA�V���J�x�[�[��p�B�������~���X�g�����Ƃ����̂������ł��܂����B�������A������ɏW���u���É����v�Ƃ��̕�e�����̏o�ŗ������A��t�ق̎�ł����z�Ⓧ������牽�ƌ����ł��傤���ˁB
�@�킽���͖S���Ȃ����c�ꂪ�����D��Ȗ��É��ق������Ă��܂����B���̂����Ƃ�Ƃ������Ղ́A�����̂ڂ�Ɣ����˂̕��m�K���̉ƒ�Ŏg���Ă������t�������ł�����A���̔��ǃG���A�Ƀ��[�c������܂��B�c�ꂪ���̐������������܂́A�������̗D��Ȗ��É��ق����ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����悤�ɁA���̐�捂Ȃ����~�X���A������͏����䂭�^���Ȃ̂�������܂���B�u�݂����v��u�Ђ܂Ԃ��v�����ł͂Ȃ��A�ق�Ƃ��ɏ㎿�Ȗ��É��̕��������Ј₵�Ă����Ă��炢�����Ɗ���Ă�݂܂���B�����ό��̂��߂ɉ�����舤�m���ɂ��z���݂̂Ȃ��܁A������p�����H��������i����u���쉀�v���אڂ��Ă��邱�Ƃł����A���Ёu�����݂̂���t�فv�ɂ������^��͂������ł��傤���B�ЂƖ������������É����y���ނ��Ƃ��ł��܂��B
 �@�@
�@�@
���E�n�����́u�T�c�L�ƃ��C�̉Ɓv�ł͂������܂���I
��
�����݂̂���t�فi���E����z�@�j�̐��ʂƑ���
��
�I�����W�F�̉������f�G�ł�
2005�N5��2���@�u��������Ȃ����A���E�T���[�v
�@�A���E�T���[����
�@
�@��������Ȃ����B3�N�Ԃ�̓��{�͂��������ł����H ���Ȃ��̋A���ɍ��킹�ă����[�X���ꂽ�V�����A���o���uBrand-New Orleans�v���A������킽���̂��Ƃɓ͂��܂����B�O��uDay Dream�v�ƁuMoon Dance�v�i�킽���̃z�[���y�[�W�ł��Љ������Ă��������܂����I�j��O�����ƂȂ��������Ȃ���A�V����v�����҂��]��ł��������ɁA�����Łu�����������v�ɏo��������l�̂悤�ɁA���Ȃ��̐V�������y���S�N�S�N�Ƒ̓��ɋz�����Ă���܂��B
�@���Ȃ����S���a�̌����̂��߂ɗ��w���ꂽ�y�n���A�����J�̃j���[�I�����Y�ł���ƒm�����Ƃ��A����͋��R�ł͂Ȃ����y�̐_�l�ł���~���[�Y�̍єz�ł���Ɗm�M���܂����B�z����Ȉ�ƃV���K�[�Ƃ����A���F�ɋP���̑��܁i��炶�j���͂����Ȃ����A�W���Y�̔��˂̒n�j���[�I�����Y�ɗ����������Ă���3�N�B���Ԃ͗��w���Ƃ��Ĉ�w�̌����������߂邩�����A��ɂȂ�ƃW���Y�E�N���u�Œn���̃~���[�W�V�����ƃZ�b�V��������Ƃ���������������i�Ƃ����̂͂����܂ł킽���̑z���ł����E�E�E�j�A�A����O�ɂ��Č��n�̃X�^�W�I�Ř^�����ꂽ�̂����x�̃A���o���ł�����A���̓��e���A���E�T���[�ƃj���[�I���[���Y�̉��y�Ƃ����̃R���{���[�V�����ł���Ƃ����̂́A�܂��������R�̂��Ƃł��傤�ˁB
�@�u�A�W�A�������Ă������ƁA�j���[�I�����Y�Ő��܂������ނ�Ƃ́A���y�Ƃ����}�̂�ʂ����������Ȃ��e���ȃR�~���j�P�[�V�����ɁA�����S������B����́A���Ƃ����l�Ԃ��ǂ����痈�����Ƃ��A�b�����t�̎�ށA�ڂ̐F�ł͂Ȃ��A���݂��̍����ǂ��Ɍ������Ă��邩�A���ꂾ�����L�[���[�h�Ƃ����S�̉��[�������ł̉�b�������B�v�@CD�Ɏ����X����A���Ȃ������C�i�[�m�[�g�ɏ��������t�ʂ�́u��b�v�����Ƃ��ł��܂��B�O���[�v�ł̉��t�����łȂ��A�s�A�m��x�[�X�Ƃ̃f���I�������߂��Ă���̂ŁA�ӂ��肾���̃p�t�H�[�}���X�ɂȂ�ƁA�u��b�v�͂��e���Ȋ����������Ȃ�A�������̂𖣗����܂��B�Â��W���Y�\���O���̂��Ƃ��ɂ́A�ǎ��ȃm�X�^���W�[��▭�ɂ��̂�����C���X�s�[�J�[���痬��Ă���̂ł��B��C�̂����X�^���_�[�g���A���Ȃ��̎�ɂ�����ƁA�܂���"Brand-New"
�Ȉ�ۂƂȂ�B�A���E�T���[�ɂ͂��Ȃ��܂���B
�@���{��ʼn̂���J�o�[�Ȃ́A���Ȃ��̃A���o�����Ƃ��̍ő�̊y���݁B���������������KURO�́u�A�t���J�̌��v�ƁA�����Ljꁕ�T�g�E�n�`���[�́u���̐U�q�v�̓�Ȃ������Ă��܂��ˁB�����Ȃ���A��Ȃ悤�ɂ݂��āA���Ƀs�b�^���Ƃ͂܂��Ă��܂��I�Ȃł��B�u�A�t���J�̌��v��I�̂́A�ז쐰�b����������������ꂽ�u��O���y�i�|�s�����[�E�~���[�W�b�N�j�̐��n�Ƃ��Ẵj���[�I�����Y�v�ɑ���I�}�[�W���ł��傤���B����u���̐U�q�v�ł́A�����Lj�̏����������f�B���A�j���[�I�����Y�̃s�A�j�X�g���e���A���Ȃ����̂��Ƃ��A���a�̂͂��߂̃��_���ȐA���n�A������C������ɂ���Â�����̏�i��������ł��邩��s�v�c�ł��B�u���̐U�q�v���u�S���v���u�z����ȁv�Ƃ����A�j���[�I�����Y�Ō������Ă����A�����ЂƂ̐�啪�����������B����Ă���̂�����B
�@���{�ɋA���Ă���ƁA�Տ��ɂ��댤���ɂ���A��t�Ƃ��Ă̐����͑��Z�ł��B�����āA�{���ɂ��������G�p���������āA���y�����Ɨ��������̂͑�ςȂ��Ƃł��傤�ˁB�������A���Ȃ��Ȃ炱��܂łƓ��l�A�����b�N�X�����p���ň�ƂƉ��y�̊������y���݂Ȃ��炱�Ȃ��Ă��܂����Ƃł��傤�B����������F�肵�Ă���܂��B�킪�܂܂ȃt�@���̊肢�́A���Ȃ��̈�����z�[���^�E���ł����邱�����É��ŁA�͂₭���C�u�������Ƃ������ƁB�u���[�m�[�g������ŁA���낻�낢�������ł��傤���H
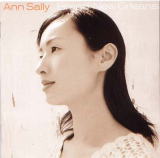
���Ƃ̓��Ȉ�ł���I�W�T���Ƃ��Ă�
���i�A���j�搶�����҂����f�@���Ă���p��
��������`���Ă݂����C�����܂�
��
�����ƁA���̉̐��Ɠ�����
�z�i���j�Ƃ����f�ÃX�^�C�����낤�ȁE�E�E

�u�ߋ��̉@��������ǂށv�ւ��ǂ�

�g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ�




 �@�@�@
�@�@�@

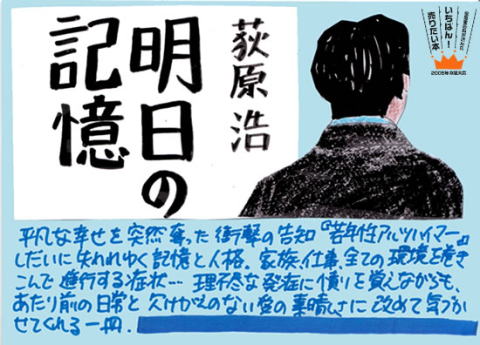
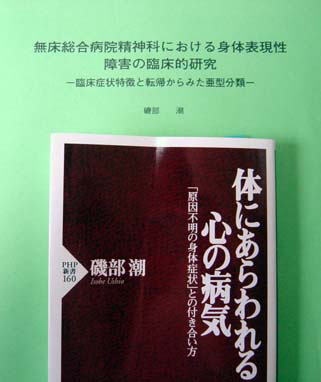
 �@�@
�@�@