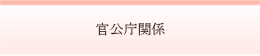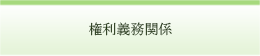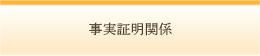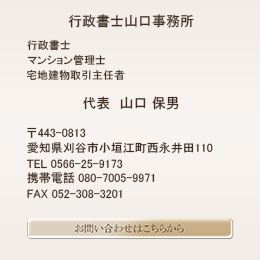1. 宅建業の免許は、こんな場合に必要です
- ①自ら宅地又は建物の売買・交換を業として行う場合。
- ②他人が行う売買・交換及び貸借について、代理又は媒介(仲介)を業として行う場合。 ※よって、アパート・マンション・テナントのオーナーは、免許を受ける必要はありません。
2. 免許には知事免許と大臣免許があります
どちらの免許でもよいというものではなく、事務所をどこに設けるかによって決まります。
- ①一つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合……知事免許 ※このとき事務所の数は関係ありません。
- ②二つ以上の都道府県内に事務所を設ける場合……国土交通大臣免許
3. 免許は誰でも受けられるものではありません
個人でも法人でも免許は受けられますが、次の一定の欠格要件(免許の基準)に 該当するものは、免許を受けることができません。
- ①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 ※未成年者は、免許が受けられます。
- ②禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受ける ことがなくなった日から5年を経過しない者
- ③宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、 又は傷害罪、傷害現場助成罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、 その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過 しない者
- ④免許申請前5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- ⑤宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- ⑥宅建業法66条1項8号又は9号に該当するとして免許を取り消され、 取消しの日から5年を経過しない者 ※「不正手段による免許取得」「業務禁止処分対象行為で情状が特に重い」 業務停止処分違反」
- ⑦宅建業法66条1項8号又は9号に該当するとして免許を取り消された者が 法人である場合において、免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前 60日以内に役員であった者で、取消の日から5年を経過しない者
- ⑧宅建業法66条1項8号又は9号に該当するとして免許取消処分の聴聞の期日及び 場所が公示された日から、処分をするかしないかを決定するまでの間に解散・ 廃業の届出をした者(解散・廃業につき相当の理由がある者を除く)で、 届出の日から5年を経過しない者
- ⑨⑧の期間内に合併により消滅した法人又は解散・廃業の届出のあった法人(合併・ 解散・廃業につき相当の理由がある法人を除く)の聴聞の期日及び場所の公示日前 60日以内に役員であった者で、その消滅又は解散・廃業の届出の日から5年を 経過しない者
- ⑩営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、 前記①~⑨のいずれかに該当する場合
- ⑪法人で、その役員又は政令で定める使用人のうちに、前記①~⑨のいずれかに 該当する者がいる場合
- ⑫個人で、政令で定める使用人のうちに、前記①~⑨のいずれかに該当する者が いる場合
- ⑬事務所ごとの法定数の成年者である専任の取引主任者を置いていない者 ※免許を受ける本人や法人の役員が主任者であるときは専任とみなされます。
- ⑭免許申請書の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が 欠けている者
4. 免許申請に必要なものは?
上記3の免許の基準に該当しないこと証する書面のほか、事務所の写真などが必要です。 また、免許の手数料として知事免許の場合は33,000円、大臣免許の場合は90,000円 が必要です。 その他、宅建業を開始するには、営業保証金を供託するか、保証協会に加入することが 必要です。
5. 免許取得後の届出等
- ①免許の更新申請 免許の有効期間は5年であり、有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請が 必要です。
- ②宅建業者名簿の変更届出 商号・名称、事務所の名称、役員の氏名、政令で定める使用人の氏名、専任の取引主任者の 氏名に変更があった場合は、30日以内に届け出る必要があります。
6. 当事務所が申請の代理をお引き受けする場合の費用
| 新規の免許申請(知事・大臣) | 50,000円~60,000円 |
|---|---|
| 更新申請(知事・大臣) | 35,000円~60,000円 |
※事務所、役員、専任の主任者の員数により、具体的な金額を確定いたします。